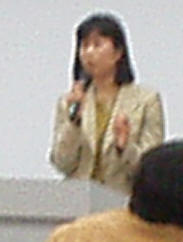
公開講座
左からベイリー先生(アメリカ史)、杉山先生(アメリカ文学)、有賀先生(アメリカ史) (平林先生、永田先生、外山先生:近日掲載)
教官コミュニティのボランティア企画 公開講座のご案内
埼玉大学教養学部主催 市民のための公開講座
「アメリカを探る」:ポスト9.11時代のアメリカ社会
-ジェンダー、エスニシティ、国家-
アピール プログラム 公開講座レポート/感想 Web管理者から
昨年9月11日の同時多発テロ事件の衝撃的な映像以来、わたしたちはメディアを通じて、さまざまなアメリカの姿にふれています。
変わり果てたニューヨークの姿、その中で家族や職場を失った人々を支えるボランティアたち。その一方で、一人を除き満場一致によ
る議会での開戦決議や、国中にあふれる国旗、国歌。「アメリカはなぜ世界から嫌われるのか」といったたぐいの記事も新聞や雑誌な
どをにぎわせています。
こういった時だからこそ、わたしたちには「アメリカ合衆国とはどのような国なのか」についての、多方面からのバランスのとれた知
識、情報をえて、合衆国をかたちづくるさまざまな文化、政治、経済などの構図を理解することが必要とされていると考えます。
今回の講座は、埼玉大学教養学部にアメリカ合衆国のベス・ベイリー先生を迎えることになった機会をいかし、ベイリー先生および、
埼玉大学教養学部の教官スタッフにより、ジェンダー、民族などマスコミ報道では見えにくい合衆国のすがたにアプローチしていきます。机上の空論でもなく、印象や感情にのみたよった刹那的な議論でもない、知の生産の成果を市民に広く公開する
機会を持ちたいと考えています。
5.25 ベス・ベイリー(ニューメキシコ大学助教授・フェミニスト・インスティチュート所長)
ポスト9・11時代のアメリカ:ジェンダー・民族・国家(通訳:杉山直子先生)
6.8 平林紀子 教授 アメリカの世論:テロ事件以後の世論に表れたジェンダーとエスニシティ
6.15 永田雅啓 教授 アメリカの経済――光と影――
6.22 菅野峰明 教授 アメリカの都市
6.29 杉山直子 助教授 アメリカの現代文学: 女性と民族を中心に考える
7.6 外山紀久子 助教授 アメリカの現代美術:抽象表現主義とその後の展開
7.13 有賀夏紀 教授 アメリカ史の視点・ジェンダーとナショナリズム
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
アメ研教官コミュニティ
公開講座レポート/感想
(学生たちのML投稿より)
埼玉大学教養学部が埼玉県男女共同参画推進センター「With
You さいたま」と共催した市民向け公開講座、「アメリカを探る::ポスト9・11時代のアメリカ社会 − ジェンダー、エスニシティ、国家 ―」の参加者のレポートです。
*************************************************************************************
第1回:5月25日(土)「ポスト9・11時代のアメリカ:ジェンダー・民族・国家」(ベス・ベイリー助教授)
・メディアの報道を通して強調された「男らしさ」のイメージは、強くたくましく、社会正義のために戦う一方で、涙を流し悲しむ男性たちの優しさ、他者を思いやる気持ちであったこと。そして、女性たちのそれは、死を悼む「犠牲者」と「慰める者」という伝統的な「女らしさ」のイメージであったこと。それらは、テロ撲滅の戦争への批判を懐柔する側面も持ったこと。
・犠牲者は救助隊、証券取引者、軍関係者の3タイプで、殆どが男性であり、職種におけるジェンダーが浮き彫りになったこと。
などなどを、報道ビデオや写真、統計資料などを使い、実証的に議論を導いておられました。
参加者は比較的高年齢層が多く、また質問も活発に出されました。特にgender equity とgender
equalityの違いについての質問には、前者についての議論では「機会の平等」や「多様性」「社会的善」といった公正さが主要な意味合いで、後者が「例えば職場で男女比率が50%対50%になること」と、両者のバックグラウンドが異なり、言葉の使われ方に議論があることを強調されておられました。
**************************************************************************************
第2回:6月8日(土) 「アメリカの世論:テロ事件以後の世論に表れたジェンダーとエスニシティ」(平林紀子教授)
・先生の講演はギャラップ社の調査に基づくデータを中心に使い、分析したものです。かなりわかりやすいデータでした。年間100ドルでデータ及び分析結果を配信しもらえること、というのがおいしいと思っ
た方もたくさんいたと思います。内容は、9.11テロ後のアメリカ世論に見るジェンダーとエスニシティ。
1 高いブッシュ支持率ーRally Aroun Flag効果
2 マイノリティ世論の特徴
3 アメリカの理想への信頼、外国は「味方」と「敵」に二分
4 今後を占う
フロアからの質問も「イスラエルの影響」「ゴアが大統領だったら」と面白いものでした。聴衆は女性のほうが圧倒的に多く、土曜日の午後というのに働き盛りの男性がたの姿がなかったのが残念です。
・世論調査をもとにこうしてみると、面白いことがわかるものですね。ギャラップ世論調査をデータに、9月11日を境に、アメリカの人々のイスラム教圏の人々・国々への意識や、対テロ戦争への意識、自国民性のイメージなどにおいて、あぶりだされて見える男女差や民族差などの話でした。調査方法や対象選択によって、こういう調査にひっかからない極貧層や業種領域などがあるそうで、ある意味で階級差や社会層のマッピングがほの見えてくるところが興味深いです。女性のほうが経済変化に対して敏感かつ大仰に反応する傾向がある、というのがおもしろかったですね。「女性のほうが男性より現実的」という「定説」(?)を果たして裏付けている?
********************************************************************************************
第5回:6月29日(土) 「多民族国家としてのアメリカ・文学的想像力におけるジェンダーとエスニシティ」(杉山先生)
1970年代以降のアメリカ文学における、古典・規範の見直しからはじまり、エスニック文学が黒人運動や女性運動を通して台頭したこと、そして、その代表的な女性作家と作品群を紹介してくださいました。杉山先生のお話はとてもわかりやすく、ひきこまれるものがあります。そのせいか、質問も活発で、時間をオーバーするほどでした。
経済や地理の講義の際に見られた質問には、結構マニアックに思えるものがありましたが、今日の質問はどれも多くの人に関心あるものだったのではないかと思います。そのうちふたつをご紹介します。
質問1)優れた作家がちゃんと認められるようなシステムがアメリカにあるか?
答え)あるといえるとすれば、それは大学で、黒人研究、女性研究、アジア系アメリカ人研究といったものに、70年代から予算がつき、学科が出来、という具合に学問として成立し、さらに研究誌ができることで、埋もれていた作家の作品がマイノリティ研究を通してピックアップされ、評価を受けるようになった。大学は依然として西洋文化中心だが、こうした研究分野の学科を置くのは大学のステイタスとして重要視されており、そうしたシステムは制度的には出来てきている。
質問2)そうした作家が大学の研究として取り上げられる事が多くなったそうだが、一般大衆の中では、どのように受け入れられてきているのか?
答え)大衆の中には、「黒人文学は黒人しか読まない」といったスタンスもあったが、それを変える様な作品が現れた。『ルーツ』(A.ヘイリー)がそれで、1978年にTVシリーズが放映されると、大プレークし、ドラマの内容が毎日の話題にのぼるほどで、本は黒人にも白人にも読まれた。
つぎに現れた作品は『カラー・パープル』(A.ウォーカー)で、これは1982−83のベストセラーとなり、スピルバーグの映画化以前に、黒人にも白人にも読まれた。ほかに『ウーマン・ウォリアー』(M.H.キングストン、邦訳『チャイナタウンの
女武者』)、また「ジョイ・ラック・クラブ』(エイミー・タン)の映画は大ブレイクした。
人気TV司会者オプラ・ウィンフリーは自分の名前の雑誌まで出しているが、彼女の番組で本の紹介をやっており、それに取り上げられた本はオプラの「O」マークをつけると、売上が格段によくなる。NYTのベストセラーリストには、たいていと言っていいほど「O」マークの本が入っているほどだ。
------------------------------
この講座シリーズには息子の出身高校のPTA仲間の友人も来ておりまして、とりわけ文学好きの彼女は講義後、ヒサエ・ヤマモトの作品をぜひ読みたいと申しておりました。私は、レズリー・M・シルコウの作品を読みたいと思っています。
*******************************************************************************
第7回(最終回)7月13日(土)「「9.11と第二次世界大戦 『アメリカの自由』、愛国心の意味」 (有賀夏紀教授)
開かれた埼玉大学を目指しての、教養学部の画期的な取り組み、市民向け公開講座「アメリカを探る」が盛況のうちに終了しました。
トリを務められた有賀先生のご講義は「9.11と第二次世界大戦 『アメリカの自由』、愛国心の意味」でした。
歴史研究視点から、レジュメには実証的な資料を添えられての非常に興味深いお話でした。
特に、アメリカの自由とは、従来私たちがイメージしてきた、言論の自由や精神的自由とは限らず、「消費文明」と一体化した物質的自由も含まれてる、というご指摘、そして、アメリカの「愛国主義」や「愛国心」には
1.政府を支持する
2.民主主義に反する政府への反対
3.「地球市民」意識から愛国心不要提唱
という3つの立場がある、というご指摘に、講座参加者の中にはため息混じりで、しきりにうなづいておられる人たちも見うけられました。
また、アメリカのメディアには色々な立場があるが、或る出来事についての認識が同時代に出来ていく上で、メディアと政府の果たす役割が圧倒的に大きい、というご指摘には、私たちのメディア・リテラシーの問題を否応なく意識せざるを得ませんでした。
**********************************************************************************
Web管理者から: 学外の人たちの反応はどんなものだったでしょうか?これについては、WithYouさいたまからのアンケート処理結果を見る必要があります。 ところで、一般参加市民のみなさんに直接たずねてみたところ、好意的感想が多く占めていましたが、公開講座が教官コミュニティの全面的ボランティア(経費、時間、作業労働提供)であることは、 ほとんど知られていませんでした。これは講座後3ヶ月経た10月に、当時の参加者の方々から直接聞いて分かったことです。「講師料は出ていると思った」というコメントが複数ありました。 実際は、レジュメ作成も交通費もすべて、企画に参加された教官先生方の自前で、完璧なボランティアでした。こうした企画の準備と実施の大変さは並大抵ではありません。しかし、今後もこうした講座が実施され、市民と大学の間に太いパイプができて行くことを期待したいものです。