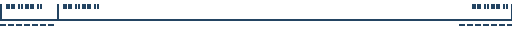
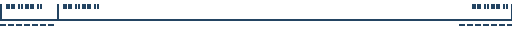
 教育方法を考える会 第1回ミーティング 報告
教育方法を考える会 第1回ミーティング 報告
(菅野峰明)
| 教育方法を考える会 第1回ミーティング 2000年5月19日 12:00〜14:00 共通研究棟5F映像メディア分析室 菅野峰明: 教養学部の授業に対する学生の意見 教養学部の自己点検・評価等委員会は,教養学部の学生が学部の教育,施設,設備などに対してどのような意見を持っているかを聞くため,各コースの代表者(コースの所属学生が50名以上の場合は2名,それ未満の場合は1名)の出席を求めて1999年12月に3回のヒアリングを行った.この結果は2000年3月31日発行の『教養学部の現状と課題』に掲載されている.そこで,掲載されている学生の意見から学部の教育の現状を捉え,そこを出発点としてよりよい教育方法を考えていくことが望ましいと考え,学生の意見を検討することにした.ここでの教育方法とは,教え方のテクニックではなく,むしろ大学の教育として何をどう教えるかに関係することである. 教育方法に関する項目ごとに学生の意見を並べ,それらに説明を付け加える形式で検討していく. 1.コースのカリキュラムについて 教養学部の教育は16のコースごとに作成されているカリキュラムに基づいて行われている.カリキュラムは各コースで何を教育するかを示したものであり,教育システムとして重要な要素である. ・学生の要望を聞きながら、次年度の講義を準備してくれるので、特に不満はない。 ・多くの授業が開講されていて、その中から選択できるので、良いと思う。→選択の可能性大 ・必修科目があまり多くないので、授業の選択の幅が広がってよい。→授業選択の自由 ・必修が少ないので、他のコースの授業を取りやすい。 ・半期の授業が多いコースでは、通年の授業が多いコースの科目を取りにくい。 ・必修科目は本当に必要なものだけにしてほしい。→コースによって必修科目の数が異なる ・カリキュラムは物足りない。 ・まとまりがない。 ・専門の授業が少ない。 ・コースの演習が同じ時間に複数あるのが困る。→教官の間での調整 ・専門分野については専任の先生が少ないので、勉強に偏りがでる。 ・コースの必修や選択必修が少し多い。→コースによる違い ・同じ曜日にコースの授業がかたまっていて時間割を組みにくい。 ・コースの取りたい講義が同じ時間に重なるのは困る。→教官の間での調整 ・演習はできるだけコース学生優先の少人数の方がよい。 ・非常勤の先生は毎回新しいから新鮮である。けれども、教授の関心に合った先生が来るから、 分野としてはマンネリである。もっと意外な分野から呼んで欲しい。 ・4月最初の講義選択期間にもう少し柔軟性があってもよい。 ・専門科目で3年間1度も開講されなかった講義があったのは残念。→教官コミティのうっかり ミスか怠慢か ・履修のシステムがわかりにくいので、前・後期の登録の際に相談ができるようにして欲しい。 ・卒業論文の進行状況は2・3年生にもなるべく公開されると、これからどのように卒論を仕上げて いくべきかが分かる。→卒論指導方法の検討 コースのカリキュラムは各コースが必修科目や選択必修科目を独自に設定しているので、カリキュラムについての学生の意見はコースの違いを反映してバラエティに富んでいる。そのため、一方では、必修科目が多いという意見があり、もう一方では必修科目が少ないという意見がある。また、コースの教官コミティの人員が異なるので、授業が多く準備されているところと、少ないところがあり、コースによって専門科目の数に違いが出てくる.コースで何を教えるか(授業科目)の検討が必要なコースもありそうである.コースのカリキュラムについて,「同じ時間に同じコースの授業や演習が重なると困る」という意見はくみ取って、同じコースの授業や演習が重ならないようにする努力が必要であろう。 2.教育・指導について(講義・演習・卒業論文の指導など) 講義,演習,卒業論文の指導については,教官個人に任されているために,教官による違いが大きい. ・卒業論文は自分の好みの先生について指導を受けられるので、とくに問題はない。 ・専門科目の講義・演習・卒業論文に関しては、おおむね満足している。 ・コースの学生数が少ないので、いろんな面で指導していただいている。卒業論文指導も先生1人 に対して学生1〜3人というのが普通なので、細かく指導が受けられる。 ・基礎演習は少人数で充実していた。 ・十分である。 ・とくに不満・要望はない。 ・学生が少ないので、こまめに指導してくれる。 ・必要に応じて、週1回あいた時間に自主ゼミを開いたりしてくれるので、不満はない。 ・毎週レポートを提出する講義は、大変だがためになる。 ・少人数のクラスが多く、指導がきめ細やかである。 ・講義では生徒との対話が少ないと思う。→一方的な講義に対する不満 ・卒業論文演習を始めるのが遅かった。→卒業論文指導体制の確立 ・レポートを提出しても読んでくれない授業もあった。→教官の手抜き ・毎年、全く同じ講義であったり、毎回30分程度遅れてくる先生がいて困る。→教官の手抜き ・先生が自分の書いた本をテキストとして押しつける授業に対しては不満がある。→ 使用しないのに教科書として買わせる ・講義は非常勤の先生の方がうまい。 ・コースによって教師や学生の熱心さが違う。 ・先生ごとに異なり、統一性がない。 ・試験・レポートはちゃんと採点して返却して欲しい。→成績評価の明確化 ・レポートは先生のコメントをつけて返却して欲しい。→きめ細かな指導の要求 ・レポートの返却を制度化して欲しい。 ・レポートの課題が出されるのが遅いので、多くのレポートを短期間で作成するのはつらい。 →レポートに何を求めるか ・講義の途中でも質問を受け付ける環境を作ってほしい。→ディスカッション中心の授業は少ない ・学生のやりたいようにやらせてくれるので良いが、もっと詳しい説明がほしい。→卒業論文か? ・演習では、もっと生徒同士でディスカッションできるような形にしてほしい。→授業運営の問題 ・黒板に書く字は、読める字にしてほしい。→テクニカルな問題 ・生徒が先生の授業評価をできるようにしてほしい。そしてそれを公開してほしい。 →授業評価の必要性 ・授業で使用するテキストはあらかじめ作ってほしい。自分の著作を買わせるのではなく、 必要な資料だけをまとめて冊子にしてほしい。→教科書の値段が高いから ・成績評価の基準をしっかり示してほしい。→成績評価の厳格化 ・先生ごとに卒業論文指導をしているが、コースの仲間がどのような卒業論文に取り組んでいる のか知りたいので、コースの卒業論文総合演習のようなものがあった方がよい。 →コースによって卒業論文指導の方法が異なる 学部の教育・指導については学生の満足度が高い。これは,少人数の授業が多いので、そこでの細かな指導に満足しているためのようである。ただし、授業がこのままで良いというわけではない。学生の提出するレポートを成績評価に使用する授業が多いが、このレポートには学生の学習活動が含まれているので、教官がコメントと評価をつけて学生に返却してほしいという要望が多い。また、一般にレポートの課題が12月の後半に示されるので、1ヶ月位で多くのレポートを書き上げなければならず、与えられる期間が短すぎるという意見もある。卒業論文の指導体制については,教官ごとの個人指導で満足しているという意見とコースの学生たちが取り組んでいる卒業論文の内容を知りたいので卒業論文総合演習が必要であるという意見がある. |
