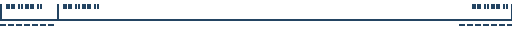
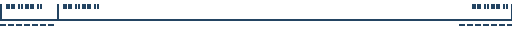
 教育方法を考える会 第2回ミーティング 議事録
教育方法を考える会 第2回ミーティング 議事録
| 教育方法を考える会、第2回ミーティング 日時:2000/06/16 12:15-14:13 場所:映像メディア分析室(共通研究棟5F) 話題提供者:高木英至 話題:何をどこまで教えるか? − 背景となる議論 出席者:高木(話題提供者)、権、永田、西坂、野中、山口、山本 (菅野代表は学生による教育実習の授業参観のため欠席) 話題提供者の高木が別項「報告内容」にしたがって報告した。主な論点は以下だった。 ・教育の質を維持・向上させるとともに、教育面で省力化する必要がある。 ・その両方の目的のために、教えるべき事項を科目ごとに列挙し、複数の授業に内容を配分することが重要だ。 ・私に近い分野では、世界的に、何を教えるべきかという点では一定の合意がある。他の領域についてはよく分からない。 その後、出席者が自由に議論を交わした。主な議論は以下だった。 ○高木の報告について ・個人としては教える事項を体系化している人が多いと思う。 ・自分の領域は1人なので、実際には全部できない。 ・体系的に教えることには利点と欠点がある。まんべんなく知識を得られるのは利点だ。自分の専門の個所で特に詳しくなれないのは欠点だ。 ・教える事項をリストアップして状況に応じていくつかの授業に配分することは、省力化になる。 ・高校までのカリキュラム削減で、高校までに得るべき知識を持たずにコースに来る学生がいる。そういた事態にも対応しなければならない。 ・国立大学の先生の中には、教育に対して無責任な先生が私立大学より多く見受けられる。いろんな事情があるのかもしれないが、コースによっては授業が開かれていないところもある。また著作を書くために平気で授業を休む先生もいる。学生に対して授業を行うのは、教師としての最低限の務めなのではないか。こうした意識改革を行っていかなければいけないのではないか。 ○授業の共通化(「部品の共通化」)について ・典型的には統計のように、分野に関わらず開くべき授業があるだろう。そうした授業を共通に開設する(「部品を共通化」する)ことを考えるべきだ。 ・学部共通で主要な授業を開設し、各コースでとらせるように考えるべきだろう。 ・部品の共通化をするならコースのグループごとだと思う。 ・書誌学などは共通化できるかも知れない。 ・地域系のコースでは、西洋史などで、共通にできる授業をつくることは可能だろう。が、可能かどうかというより、意思の問題が大きい。 ○教科書の問題 ・同じ分野の英語のテキストを見てみると、章立てだどはそれぞれ個性がある。しかし盛り込まれている内容は外見以上に共通性がある。 ・どのテキストを使うかの選定は大問題だ。悪いテキストを使うと勉強したい学生を discourage することになる。 ・自分は、教科書を使う授業は大学に入ってから受けたことがない。 ・教科書の選定基準をどうしているか、同僚に調査してみたい。 ・自分は、教科書を使うかどうかは授業による。 ・教科書は使わないけれど、本のリストを学生に渡して読むように指導している。 ○学ぶことは学生にとって何の意味があるのか?(「学生の満足度」から話題が派生する。) ・教養学部は選択の幅が広いために学生の満足度が高くなるようにできている。不合理な、不要な拘束が少ないことは良い。 ・学生はお客さんであり、学生の満足度も重要だ。が、一方で学生は大学にとって商品という意味がある。学生を商品と見たときに教養学部の現状はどうなのか? ・自分たちが教えていることは、直接は役に立たなくても、総合的な力になっていると思っている。 ・私は学生を商品とは考えていない。市場で自分の労働を売っているのは学生自身であり、大学ではない。大学がろくなことを教えなければ学生は大学を求めなくなるだろう。でも人目には変な商品でも、売れれば需要があると考えるべきだ。 ・人間は役に立たないことでもやるものだ。 ・スポーツでも勉強でも、企業は何かをちゃんとやった人間を採ろうとするだろう。 |
