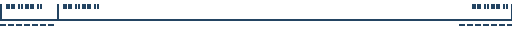
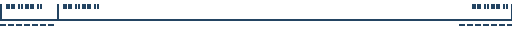
 教育方法を考える会 第4回ミーティング 議事録
教育方法を考える会 第4回ミーティング 議事録
| 教育方法を考える会、第4回ミーティング 日時:2000/11/17 12:10-13:30 場所:映像メディア分析室(共通研究棟5階) 話題提供者:野中進 話題:レポート、論文作成の指導について 出席者:野中(話題提供者)、菅野(代表)、永田、山本、市橋、高木 ○話題提供者の報告からミーティングを始めた。報告の要旨は次のようだった。 ・スラブ文化コースで論文を書く授業を作っている。出席者にあてて発表をさせる形式で、文献を読んで文章にまとめることを義務化している。 ・その授業のために作ったのが(別項資料の)「論文・レポートの作成(考え方のまとめかた)」です。 ・次のような状況を改善したいと考えた。論文と本の区別がつかない学生が多い。報告をさせると、本の記載をつぎはぎしたような報告をする学生が多い。 ・この場ではレポート・論文指導の問題点を discussできるとよい。例えば、レポートを返却してほしいとか、レポート題目を早めに出して欲しい、といった要望が、菅野先生の報告による学生の要望のインタヴュー結果でも出ていた。 ○以後、次のような議論を交わした。 ○レポート・論文作成の授業について ・野中先生の資料は学生に配った資料か? また、授業の効果はどうか? ・授業で配った。この授業を難しいと思う学生もいる。レポートを本のつぎはぎでよいと思っている学生もいる。授業をして実力が伸びたと思う学生も若干いる。 ・体系的に論文指導をした方がよい。以前の授業で、アメリカ研究コースの学生のレポートが良かったことが記憶に残っている。たぶん有賀先生の授業で体系的な指導をしているのだと思う。この種の授業をすると教育効果ははっきり出る。 ・論文作成の授業では文章の数をこなして訓練すると効果がある。この種の訓練を論文指導の授業でやるのがよいか、普通の授業に導入するのがよいかは、判断の余地がある。 ・文書作成の授業がよいのか、基礎演習でやるのがよいか、という問題が以前から出ていた。一方で、必修であった方がよいかどうかの判断も必要だ。 ・基礎演習の(学生の)状況は論文作成以前の段階だと感じる。 ・基礎演習は確かにそれ以前の段階だと感じる。私は文献の集め方、地図の読み方などを指導している。 ・私もスタイル、表記法を教える段階である。基礎演習では文書の中身の指導まではいかない。 ・基本的な問題として、事実と意見の区別が出来ていない学生が多い。 ・学生の頃、物理などのレポート書きの訓練をさせられた。この場合、結果と考察を区別する書式が出来ていた。そうしたレポートを書いているうちに、書き方が分かるようになったと思う。 ・上智大学ではスタイルに関する小冊子を学科単位で出している。論文の書き方などをまとめている。この小冊子を見ると、分野ごとのスタイルが分かる。 ・文書の書き方をどういう方法で教えるのがよいか? 学部全体で行なうか、下位単位に分かれて行なうか? ・(少なくとも)2つくらいに分けて出来るのではないかと思う。 ・演習で学生に発表させるときは他の学生にコメントさせるとよいと思う。学生にはスタイルを意識するようにさせている。 ・人の論文を報告させるとよい。 ・論文を学会の評価項目で評価させたことがある。が、学生には難しかった。 ・自分の学部時代、院生などの文章を見て学習したと思う。身近にそういう院生がいるとよいが。 ・短い文書でよいものを書くのと、長い論文を構想させるのとは別のようだ。短い文書をうまく書く学生の中には、長いものを構想できない者もいる。 ・私の場合、論文を読ませ、アブストラクトを報告させるようにしている。 ・私の場合、論文読みをさせると内容以前のところでつまずくのをよく見る。例えば統計の知識がハードルになってしまう。論文以前に統計などをちゃんとやらせないといけないと感じている。 ○卒論について ・卒論は青春の思いのたけを書けばよい、という考えを持っている人がいる。われわれの(学術的なものを書かせるという)要求と社会一般の要求は食い違っている、ということはないか? ・卒論を書く能力は一般社会でも有益だと思っている。 ・卒論の訓練は、広い意味での情報処理能力を養う、ということだ。 ・私は学生にメモ用紙を配り、考えをメモさせるようにしている。広告マンなども同様にアイディアをメモに書くと聞いている。学問的な文書を書く技術はそうした面でも実際的に有益だろうと思う。 ・企画書などを書く機会は実社会に出てもあるだろう。しかし学生の中で論文を書くことの重みがどの程度かは分からない。 ・私のコースを見ていると、卒論重視という名目が悪い結果をもたらしていると思う。演習では学生が自分が決めたテーマで報告をするようだ。教官は文献などを教えるという。こうなると卒論演習との差がなくなる。極端に言うと、学生は1つの報告を持っていろんな授業で単位をとることもある。だけではなく、自分の勉強以前に習得させるべきことを習得させずに終わってしまう。学生が自分で勉強することは良いことに違いないが、基礎的な勉強をまずさせるべきだ。また、自分の勉強は卒論として活かせばよい。卒論は卒論で単位になる。演習は他の授業と同様に独自のテーマを持た なければおかしい。 ・演習をどのように行なうかにもよるだろう。 ・私のコースでは演習は全教官でやっている。3年生向けの演習では、4年は3年生の前で報告する。 ・卒論演習にはおかしなところがある。時間割に載っていない。 ・私は卒論は必修ではなく、選択制でよいと思っている。論文は日頃研究をしている人が、書くべきことが見つかったら書くものだ。すべての学生が研究している、という訳ではない。 ・卒論を書くことは、本来、honorと考えるべきだ。その他の学生には、基礎的なことを身に付けさせた方が現実的だと 感じる。 ・卒論でどのくらい落すか? 問題がある卒論には出会ったけれど、私はまだ落としたことがない。 ・私も落としたことはない。 ・実際に落としている例もある。 ・卒論の成績は優が多いか? ・優以外もつける。 ・優以外もつける。が、卒業する学生へのご祝儀として、私は優が多い。 ・演習もとらずに卒論指導の依頼に来る学生がいる。 ・卒論演習はどのようにやっているか? ・私のコースでは教官ごとになっている。コースの全教官で一緒にやった方がよい。 ・一緒にやっているコースが多いはずだ。 ・私のコースでは教官によってディシプリンが違うので、一緒にやる意味はない。別にやっている。むしろ、他の大学の非常勤の先生(同分野)と一緒に卒論演習をしている。 ・卒論に何を求めるか? ・それほど大仰な論文を求めるのは間違っている。 ・卒論にも Small is beautifulという原則があると思う。内容を特定した論文が良い論文になる。しかし漠然とした テーマを持って来る学生がいる。 ・演習問題のような形で卒論をやらせる、ということでよいのではないか? ・簡単にデータが集まるようなテーマが結構ある。そういうデータをいじって分析する、ということでも、論文に必要な要素が揃うことが多いと思う。なるべく具体的なデータをいじらせると論文としてまとまりやすい。 ・(領域は異なるが)私も資料があるテーマで卒論を書かせる。その方が面白い研究になる。1次資料、研究すべき対象の時間・場所を特定して学生に指示する。 ・卒論ではオリジナリティを要求するか? ・私はオリジナリティを気にする。ただし(文献の)サーヴェイ型の卒論も認める。 ・私はサーヴェイ型の卒論は認めない。 ・サーヴェイしさえすればよい訳ではない。文献のまとめ方にオリジナリティがあること(独自の観点でまとめること)が必要だ。 ・卒論指導の際に学生を手助けするか? ・私は学生の調べられる範囲でやらせる。が、本人の能力を超えるところはこちらで用意してあげる。 ・手助けといっても、図書館に連れていくことくらいだ。資料・文献の現物を見せる必要がある。 ○参加者の次の予定があるためにここで議論を打ち切る。 次回は以下の要領でミーティングをすることで合意する。 日時:12月15日(金曜)12:00− 話題提供者:永田雅啓 |
