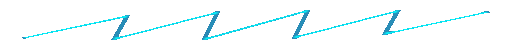
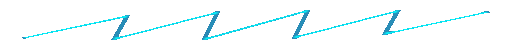
| 予定 | 実際 | |
| 10月2日 | ガイダンス | ガイダンスをした。授業の進め方を説明した後に、USA
Counties 1998 のデータに基づく分析例(前期の社会心理学演習Ⅱで出席者が分析した結果)の解説を行った。 話し合いの結果、次をテキストと決めた。 東京大学教養学部統計学教室(編) 『統計学入門』 東京大学出版会 生協書籍部で確認したところ、10月3日には入荷するとのことだった。次の授業時間に渡せます。なるべく釣り銭なしで代金(定価2800円のところいくらかは不明)を用意しておいてください。なお10月4日(水曜)以降なら高木の研究室に来れば渡せると思います。 重要:来週(10月9日)は休日だったので、10月9日に全員にテキストを渡すことができなくなりました。受講者はなるべく早く高木の研究室にテキストを取りに来て下さい。高木がいないときは3階資料室で本を受け取ってください。なお、本を受け取ったかどうか、代金を払ったかどうかをチェックしておいてください。代金(2400円)は後で結構です。10月16日からこのテキストの内容で授業に入ります。 |
| 10月9日 | 休日(体育の日) | 休みは休むもんです。 |
| 10月16日 | 統計への導入。テキスト第1、2章 | 1、2章について、高木が思いつくまましゃべった(だけ)。質問が出なかったですから。来週の個所(3章)は、そうやすやすとは分からない思いますので、よく読んでおいてください。それと、自分なりの疑問点をハッキリさせるように心がけてください。 |
| 10月23日 | 第3章(2次元のデータ) | 第3章を終了した、ことにする。 本日もゼーンゼン質問が出ませんでした。分かっていればよいけれど、そうではないと思います。 次を次回までの課題としました:テキスト pp.64-65 の「練習問題の3.1」レポート用紙に書いて次回の授業時に提出してください。 |
| 10月30日 | 第4章(確率)と第5章の一部(5.1, 5.2) | 予定の個所(左記)について話す。 先週出した課題を回収。気がつかなったですが、この練習問題は解答が載っていたんですね。ただ、相関係数の出し方が分からない人が結構いるのが分かったのが収穫?でした。理解するようにしておいて下さい。 |
| 11月6日 | 休み。むつめ祭整理のため休講日。 | ・・・・・ |
| 11月13日 | 第6章の一部(6.6)と第8章[10/30提出の課題ができていない人が多いので、以前の個所の復習をします。(22/11/12)] | 前回言っていた「ポーカーの手の出現率の実験」について、文書にしてきた人が2名いたことは収穫でした。 最初に相関係数の計算の仕方を議論する。ついでテキスト6.6(正規分布)についてシミュレーションとともに解説する。第8章までは進めず。次回までに9章まで読んでおくこと。 次回までの各自の課題:P.122 の「<例> 偏差値得点」の個所を、「付表1 正規分布表」(p.280)と対照しながら理解できるようにしておくこと。 |
| 11月20日 | 第9章と第10章[正規分布表の見方、および第8、9章まで進む予定 (00/ 11/ 13)] | 正規分布表の見方から始め、8、9章を一応終える。次回の10章の部分が非常に重要になるので、繰り返し本を読んでおいて下さい。正規分布と t 分布を混同しないように。 |
| 11月27日 | 第11章(推定) [10章(00/11/21)] |
10章について多少解説した。一応、10章を終わったことにしよう。 アドヴァイス:テキストを読んで分からないことがある場合、以前出てきた個所が分かっていない場合が多いと思います。分からない用語を末尾の索引で調べ、前の個所を読むようにしてください。必要に応じて高木に質問をお寄せください。 次回までの宿題:テキストの練習問題3問(以下)に、途中経過を詳しく説明しながら解答し、レポートとして提出すること。210~211ページの10.2、10.5、10.7の3問です。 レポートは返却しますが、12月9日(か10日)に飛び込みで学会報告が入ったので、新年になってから返却することになると思います。 |
| 12月4日 | 第12章(仮説検定) [11・12章(00/11/27)] |
前回の宿題のうち、10.2の説明をして時間が終わる。トホホですね。 授業中に申しましたが、この授業で予定していたレポートの1回目分(回帰分析より前の部分)は、同様の何回かの宿題提出に換えます。 (宿題=レポートは返却するつもりですが、諸般の事情から、来年になると思います悪しからずご了承ください。) 次回は11、12章を読んでおいてください。また、テキストの練習問題から宿題を出します。 |
| 12月11日 | 12月4日の補足 [11・12章(00/12/04)] |
一応、11、12章をやった、ことにする。質問を伺い限りまだ理解度は水準に達していないので、今後どうフォローするかは、正月明け提出の次の宿題の出来を見て判断します。 次回までの宿題:テキストの練習問題4問(以下)に、途中経過を詳しく説明しながら解答し、レポートとして提出すること。 11.5、11.7(231ページ)、および、12.2、12.3(252ページ)です。 |
| 1月15日 | 第13章(回帰分析) 予定:第11、12章の復習 (2000/12/11) |
ここまでの宿題レポートを返却する。 前回の宿題のうち、11.5と11.7について解説する。本日宿題レポートを提出できなかった者は来週提出、とする。なお、本日提出していても、来週再提出してもよい。 |
| 1月22日 | 回帰分析・補足 予定:第11、12章の復習。復習の必要がないようなら第13章に入る(回帰分析) (2001/01/15) |
前回の宿題のうち、練習問題12.2と12.3について解説する。なお、この授業の単位が必要なら、宿題はすべて提出してください。 この授業の範囲の内容は、従来の学生の多くが一時的にせよくリアできた範囲の内容です。テキストを繰り返して100回くらい読めば分かるはずです。1回しか(も)読まなければ分かりません。テキストは例年よりやや難しい内容です。が、そのテキストも出席者の希望で決めたものであり、詳しくは書いてあるものの、特に難解ではありません。 |
| 1月29日 | 回帰分析・補足 予定:ここまでの授業の質問、および回帰分析に関する概説的説明をします。(2001/01/22) |
学生があまり来なかったので早めに止める.ヤレヤレ.単位要件などを説明する. 未提出のレポートのある人は早めに高木に出してください. |
 メール |
 問合せ |
 Up |
