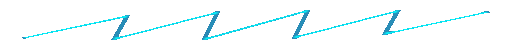
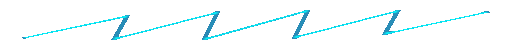
 |
テキストは次と決めました。 東京大学教養学部統計学教室(編) 『統計学入門』 東京大学出版会 実を言うとこの「統計解析」という授業はこの数年低調でした。統計を勉強する学生の意欲が低下していたことに対して私は戸惑いを覚えていました。なぜなら、現在はどのようなことを研究するにせよ、統計の扱い方、あるいは統計の考え方が身についていないと、研究は進められません。実社会に出ても統計の基礎を身につけている必要性はますます高まっていると思います。その意味で、提示したテキストの3つの選択肢のうち、私が「一番難しい」と表現したテキストが多数決で選ばれたことに、私は気を良くしています。 |
 |
あらためてテキストに選んだ『統計学入門』の構成を眺めてみました。この本はテキストとして、次の2点に特徴があると思います。第1に、私が今までやって来た統計の授業に比べ、統計の基礎概念にかかわる部分の比重が大きいことです。たぶん著者が統計の専門家であることによると思います。第2に、最後の13章(回帰分析)の内容が最初の方の第3章(2次元データ)の中で予描されていることです。この第2点はなかなか興味深いことだと思っています。たぶん「回帰分析を理解できるようにする」ことを目標にこのテキストが構成されているのだと思います。 |
 |
原則としてこの本は入門テキストですから、全部読んで理解するのがよいのは確かです。が、このテキストは4単位の授業にすることも想定されていますので、難しい個所はとばすことは仕方ありません。目次の前のページで「本書の使い方」が書いてあります。その中の「文科の学生」向けの指示に従っておくのが現実的だと考えています。この指示に従い、5-8章は一部だけを扱う(理解することを受講者に求める)ことにします。 授業の進度、従ってテキストの該当個所(の予定)は「予定と連絡」のページに書いておきます。 |
 |
気づきませんでしたが、10月9日は体育の日で休日でした。「予定と連絡」のページで書いたように、10月16日からテキストの内容で授業を始めます。なるべく早くテキストを手にして読んでおいて下さい。10月3日(水曜)以降、3階の高木の研究室にテキストを取りに来て下さい。高木が研究室にいないときは、3階資料室でテキストを受け取れるように頼んでおきますので、3階資料室に行ってください。その他、必要があれば高木にまでメールでご連絡下さい(↓)。 |
 |
一言補足します。テキストを読んで分からなくてもいちいち気にしないで下さい。統計は普通、ちょっと勉強しても分からないものです。私は大学1年のとき、統計学の4単位の授業をとりました。一応単位はもらいましたけれどよく分かりませんでした。大学3年か4年のとき、経済学部に統計の授業を聴きに行きました。その授業の先生はT先生という、大変高名な先生でした。授業が始まったときには受講者は大教室一杯でした。が、期末試験のときには出席者は驚くほどわずかでした。聴けば「Tゼミ+α」とのことでした。大体がドロップアウトしていました。数学が必要な経済学部でさえそんなものでした。私は再び授業をとったのですが、まだ分かった訳ではありませんでした。このように、統計は何度か授業に出てやっと分かって行くものだと思います。 ですから細かいことをいちいち気にする必要はありません。理解に向けて前進できればよいのです。 ただ、統計には背後に方法、思想、のようなものがあります。そうした方法としての統計の考え方は、科学的思考の基礎となります。しっかり身につけるべきだと思います。 分からない点はなるべく、授業なり、メールなりで質問するように心がけて下さい。 |
 メール |
 問合せ |
 Up |
