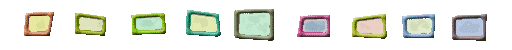
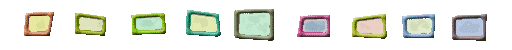
 予定と連絡
予定と連絡| 予定 | 実際 | |
| 4月16日 | ガイダンス、 A.研究法の基礎概念。次回までに読んでおく資料(文献コピィ)を配布する。 受講者はテキストを注文しておくこと。 |
ガイダンスをして、来週の議論のための資料(文献コピィ)を配り、担当者を決めた。次回までに全員、資料を読んでおくこと。 |
| 4月23日 | 配布プリントの内容を議論する。追加的なポイントを教官が講義する。連休用の宿題を出す予定。 | 前回の配布資料(Exploring Research, Chap.1)を報告してもらい、高木が解説する。 宿題:次回(5/7)の授業中に次のレポートを提出すること。前回(4/16)配布した「授業用練習問題」の問題1〜問題3への解答(自分の考え)を、レポートとして提出せよ。長さ、形式は自由。5月7日の授業では解答の説明を求めるので、あてられたら自分の考えを説明できるようにしておくこと。なお、「授業用練習問題」は隣の「授業プリント」のページで参照できます。 |
| 4月30日 | 休講 | そりゃ、休みだから、休みます。 |
| 5月 7日 | 宿題に関する議論。調査の質問項目を考える。 | 宿題レポートを提出してもらう。 宿題(授業用練習問題)の議論をして終わる。次週以降、テキストの担当者が担当部分を報告することによって、授業を進めます。 |
| 5月14日 | 4月16日のプリントの範囲を説明する。 | 統計的推測と検定の基本的な考え方を説明する。 次回までに各自、今日の授業の範囲について疑問点を整理し、何が疑問かを表現できるようにしておくこと。 |
| 5月21日 | テキスト(『社会心理学研究法入門』)の第5章(さまざまな研究法)と第6章(測定の基礎)。担当者:阪井麻衣、清水繭子、広池香奈。出席者は全員、テキストの学習範囲を読み、疑問点などを整理しておくこと。 | 第5章終了。6章の「6−3.尺度の水準」まで終わったことにします。 |
| 5月28日 | 第6章(測定の基礎)の「6−4.信頼性と妥当性」から6章の終わりまで。なお、信頼性については高木が若干の補足をします。 時間が余れば第7章に入ります。(担当:小澤、金田、横山。) テキスト(『社会心理学研究法入門』)の第7章(実験法の実際)。担当者:小澤亜由実、金田光代、横山由紀子。出席者は全員、テキストの学習範囲を読み、疑問点などを整理しておくこと。 |
第6章(測定の基礎)の「6−4.信頼性と妥当性」の個所について授業を行った。信頼性に関し、高木のプリントに書いた事項については来週に説明をします。 |
| 6月 4日 | ・高木がプリントに書いた、信頼性に関する事項の説明。 ・テキスト(『社会心理学研究法入門』)の第7章(実験法の実際)。担当者:小澤亜由実、金田光代、横山由紀子。 ・出席者は全員、テキストの学習範囲を読み、疑問点などを整理しておくこと。 |
プリントの信頼性に関する事項の説明で終わる。予定、遅れてます。 |
| 6月11日 | ・第6章(測定の基礎)の終わりの個所(残り)。 ・テキスト(『社会心理学研究法入門』)の第7章(実験法の実際)。担当者:小澤亜由実、金田光代、横山由紀子。 出席者は全員、テキストの学習範囲を読み、疑問点などを整理しておくこと。 |
第7章が少し残る。次週には第8、9章を議論します。各自、テキストを読み疑問点を整理しておくこと。 |
| 6月18日 | 第8章(観察法の実際)と第9章(調査法の実際)。担当:菊池、工藤、中本、山口。 |
第8章の途中で終わる。 |
| 6月25日 | 第8章(観察法の実際)の途中から。観察に関して高木が補足します。信頼性の個所に注意してください。第9章(調査法の実際)に入ります。担当:菊池、工藤、中本、山口。 | 8、9章を終わる。 |
| 7月 2日 | 休講(海外の学会出席のため) | |
| 7月 9日 | 第10章(態度・性格尺度の構成)。担当:第2グループ | 第10章を終了。因子分析について補足する。 次回までの宿題:授業で配ったプリントにある表6・2、表6・3を見て、因子Ⅰ〜Ⅲが何を意味するかを考え、レポートとして提出せよ。提出は次回(7/16)の授業中。 |
| 7月16日 | 第11章(データの整理と分析)。担当:第3グループ | 11章の(2)度数の検定まで(p.183)を終わる。テキストの第5章から p.183 までを7月30日の試験範囲とします。 |
| 7月30日 | 期末試験 | 試験を行う。 まだ答案をちゃんとは見ていませんが、全般的にできていません。 |
 問合せ |
 メール |
 戻る |
