卒業論文の書き方:技術編
2002.06.05
高木英至
◇この文書は卒業論文を執筆する際の技術的な注意事項を述べる。社会心理学で卒業論文を執筆する学生を対象とする。
◇あらゆる論文に適用できる手引きではない。一般の論文では許されない記述もある。たとえば多くの学術雑誌では注は許されない。
◇この文書の内容は木下(1981,1990)、埼玉大学教養学部地理学研究室(1987)、田中(1983)に基づく。高木の趣味も加味した。永山(1992) も良い本である。参考にしてほしい。
練習問題 解答はこの文書の最後にある。
Q1.「大気中の二酸化炭素は年々増加の傾向がある。今後も増え続けるとすれ
ば世界的規模で気候が変わり、河川の水量にも影響が出てくる」という論
文の題名はどう付けるか。[田中(1983:10)より]
Q2.次の数字の書き方は感心しない。どう書くがよいか。
1.1ケ月に2・3回、 2.数10人から数100人、 3.3〜400人、
4.1000円札、 5.12指腸、 6.第2・4半期、 7.20日ネズミ
[田中(1983:33)より]
Q3.「すらっとした脚の美しい黒人の娘」は何通りに解釈できるか。
[田中(1983:43)より]
◇◇ 目次 ◇◇
A.論文の構成 ------- 1
題目、全体、表題紙、要約、序文、
目次、本文、後書き、その他
B.文章の書き方 ------- 4
原則、章・節、段落、センテンス
C.表記法 ------- 7
原稿用紙、用字・用語、注、
文献リスト、文献引用、図と表
引用文献 ------- 12
問題解答 ------- 13
A.論文の構成
題目
A1.自分が論文で主張しようとすることを一つの文(目標規定文)で表してみる。
例:この論文は、他者の印象を形成する際、他者の話の内容よりも他者の話し方や身ぶりの方が大きな影響を及ぼすことを示す。
A2.目標規定文を簡潔・明快に表現する題目をつける。分析する内容を具体的に連想させない題目は改めた方がよい。
例:○印象形成に対する話し方と身ぶりの効果
○交渉過程における準拠点の影響
×生きられる世界の地平
A3.論文内容の理解を助けるような副題をつけるとよい。
例1:交渉過程における準拠点の影響: Framing 理論の適用
例2:対人関係における容貌の役割 − 美人は常に得をするか?
A4.人の注意を引きやすい主題目をつけ、主題目を補足する副題をつけるのも一つの方法である。下品な表現にならないように注意する。
例1:美人が得とは限らない:犯罪行為の帰属分析
例2:お暑いのがお好き − 余暇時間利用の季節変動
全体
A5.「一文書一主題」主義を貫く。全体の目標規定文(A1)から外れる内容を論文に盛り込もうとしてはいけない。
A6.論文の目標(仮説の検証など)を確認しつつ、目標をうまく達成する論文の構成、情報の配列順序を考える。
A7.次の構成を標準と考えるとよい。
表題紙
要約
序文
目次
本文
後書き
注
引用文献表
付録
表題紙
A8.表題紙には論文題目、所属(大学・学部・学科・コース)、学籍番号、氏名を書く。
要約
A9.要約には主題の説明と主たる結論を簡潔に1000字程度で書く。単に「・・・を分析した。」「・・・を論じた。」と書くだけではまずい。分析していかなる結論を得たかを明記する。
A10.要約に必ず目標規定文を入れる。
A11.要約は潜在的読者にその論文を読むべきか否かの判断材料を与える。無価値な論文ならいかに無価値か分かるように要約を書くのが、執筆者の責務である。
序文
A12.序文には可能な限り以下を盛り込む。
a.目標規定文(解き明かそうとする問題は何か)
b.その問題がなぜ重要か
c.論文でその問題をどのように解明するか
d.論文の構成の説明(各章が何を扱うか)
A13.次の条件がともに満たされる場合は序文を省略してよい。
a.要約がある。
b.本文が標準形式(問題の所在−方法−結果−考察、A19)にしたがっている。
A14.序文は後書きとともに、最後に(本文作成後に)書いた方がよい。
目次
A15.目次には論文の構成(章・節など)と章・節等の開始頁数を書く。
A16.本文以下の頁には算用数字を割り当てる。表題紙から目次までの頁にはローマ数字(i, ii, iii,
iV)を割り当てる。ただし表題紙には頁数をつけない。
A17.頁割り当て後に新たな頁を差し込みたい場合は、直前の頁数にa、bなどをつけた頁数を差し込む頁に割り当てる。
例:15 頁と 16 頁の間に”15a”の頁を差し込む。
A18.図と表にもそれぞれ通し番号をつけ、目次の中に図目次、表目次を入れる。
本文
A19.データ分析を含む論文の本文は次の構成を標準とする。
第1章 問題の所在
第2章 方法
第3章 結果
第4章 考察
データ分析を含まない場合も同様の章立てで論文を構成する。
なお全体の分量が短い場合は、「章」ではなく「節(§)」でよい。便宜上、以下では論文が章からなると仮定する。
A20.内容に応じて方法や結果の章を複数にしてよい。各章中に複数節を設定してもよい。章の長さがなるべく均一になるよう留意する。
A21.問題の所在の章には可能な限り以下を盛り込む。
a.取り上げる問題に関する学説・知見のレヴュー
b.まだ解明されていない点(自分が取り上げる問題)は何か?
c.自分の仮説、その仮説の根拠
d.自分の仮説の(学問的・実際的)意義
A22.方法の章ではデータ収集法、データの性格、データ分析の方法などを書く。別の人が同じ分析を再実施できる程度に詳しく書くのが望ましい。
A23.実験データを使う場合、方法の章では少なくとも以下を記述する。実験手続きの概略、実験室の状況、要因の操作法(条件の説明)、被験者(募集法・条件別人数等)、従属測度・質問紙測度の説明、操作仮説の説明、など。
A24.論文が調査データに基づく場合、方法の章では少なくとも以下を記述する。調査を実施した日時・場所・状況、用いた質問項目の説明、統計モデルと従属変数・独立変数の説明、など。
A25.結果の章では仮説との関連を常に考慮しながら分析結果を記述する。
A26.有意水準を緩くても 5% 水準に設定する。
A27.仮説に合致しながら 5% の有意水準に達さず、10% の有意水準には達する結果は、「マージナルに有意(marginally
significant)」な結果と考える。
A28.考察の章には可能な限り以下を盛り込む。
a.結果の概略(仮説が支持されたか否かの総合判断)
b.得られた結果を説明し得る、自分の仮説以外の代替的仮説の検討(もしあれば)。可能なら、代替的仮説を棄却する根拠を記述する。
c.得られた結果の含意の考察(学問的含意、社会生活への含意、政策的含意など)
d.残された課題
後書き
A29.後書きで実質的な議論をしてはならない。後書きはなくてもよい。
A30.後書きには以下のa.とb.を書く。
a.執筆後の感想
b.研究協力者、資料提供者への謝辞
ただし極度の興奮状態を示す感想、大言壮語に類する感想は、見苦しいので慎しむ。また教官への機嫌とりを連想させる謝辞も避ける。
その他
A31.注・引用文献についてはC.を参照せよ。
A32.上記(A7)のように注を本文の後にまとめるのは一つの方法である。各章の末尾にその章の注をまとめて書いてもよい。
A33.研究に用いた質問紙、実験教示、コンピュータ・プログラム、計算結果出力、新たに考案した指標の説明、数学的証明、研究に使った特殊な器材の仕様の説明、などを付録として添付する。
A34.付録をフロッピィ・ディスクやヴィデオに収めて提出してもよい。
B.文章の書き方
原則
B1.[重点先行主義]重要な論点(結論)を先に書き、結論を支持する議論を後に続ける。論文全体、章・節、段落の各レヴェルにおいてこの重点先行主義を守ると、逆の場合よりも読者は内容を理解しやすい。要約を論文冒頭にお くのは重点先行主義を論文全体に適用した結果である。
B2.[概観から細部へ]章・節、段落の各レヴェルにおいて、最初にまず内容の概観を述べ、次に細部を述べるようにする。「概観から細部へ」の原則によって、読者は現在読んでいる箇所が何なのかを把握しやすくなる。
B3.細部の記述において、情報をどの順序にならべれば効果的に目標を達成できるかに配慮する。
B4.論文全体、章・節、段落の各レヴェルにおいて、明白な道筋にしたがった文章を書く。わき道にそれる議論には次の何れかの処置をとる。
a.削除する。
b.注に落とす。
c.最後(全体・章・節の最後)でまとめて議論する。
B5.事実と意見(判断)を区別して表現する。
例:
・大学のフットボールは衰微しつつある。−意見
・多くの大きな大学では、フットボール・チームの経費が入場料収入を上まわる速さで増加しつつある。−事実
・〜説は信憑性がある。−意見
→〜説は信憑性があると私は判断している。[そして自分の判断の根拠を次に述べる。]
・〜説は一般に受け入れられている。−意見
・以下の諸研究は〜説を支持する結果を報告している。・・・−事実
・M.Weber は精緻な議論をする学者である。−意見
・M.Weber の権力概念を踏襲した著作には以下がある。・・・−事実
B6.事実を主体とした論文を書く。原則として事実の裏打ちのない意見を記述してはならない。
章・節
B7.章・節の目標(その章・節で何を述べるのか)を明確にする文(章・節の目標規定文)を、章・節の冒頭におく。
例:この章は前章で述べた方法で実施した回帰分析の結果を提示する。
B8.章・節で述べる内容の概観を与える文章(文もしくは段落)を、章・節の目標規定文の後に続ける。
例:この章は前章で述べた方法で実施した回帰分析の結果を提示する。まずロックの流行指標を従属変数とし、景気指標を独立変数とした時系列回帰分析の結果を示す。次に演歌の流行指標を従属変数とした同様の回帰分析の結果を述べる。
B9.章・節の中身を適当に小見出しで区分すると分かりやすい。
例:
ロックの分析(小見出し) 表2−1はロック流行指標を従属変数としたときの時系列回帰分析の分散分析表である。表2−1に明らかなように、・・・
段落(パラグラフ)
B10.段落の冒頭では一文字下げて書く。かっこ類の起こし − (や「 − で書きはじめるときは一文字下げない。
B11.[一段落一トピック主義]段落では一つのトピック(小主題)について述べる。
B12.段落には必ずトピック・センテンス(段落の主題を述べた一文)を入れる。
B13.トピック・センテンスは段落冒頭におくのが望ましい。よく書けた文章では、各段落の第1文を読んでいくだけで全体の内容を正しく理解できる。
B14.段落中のトピック・センテンス以外の文は次の何れかでなければならない。
a.トピック・センテンスを具体的に、あるい は詳しく展開した文
b.当の段落と他の段落の関係を示す文
B15.一段落の長さの標準は 200 〜 300 字である。
B16.一つの文だけからなる段落を書いてはいけない。ただし次の場合は例外である。
a.主題(話の流れ)を変えるための文、
しかも
b.その文を前後の段落に入れると不自然になる場合。
例: では上記と同じ原則は専業主婦にも適用できるだろうか?
[この文だけで一段落]
センテンス(文)
B17.一文をなるべく短くする。長い文は複数の短い文に分解するよう努力する。
B18.複雑な構文を避ける。一文を短くすれば自ずと単純な構文になる。
B19.前置修飾節を少なくする。例えば文を分解して前置修飾節を前に出す。
例:貢献であるインプットと成果であるアウトプットが釣り合っていない不公平状態は、さらに行為者がインプット以上のアウトプットを得ている不公平−有利状態と、アウトプット以上のインプットを貢献している不公平−不利状態に分類される。
→ 不公平状態ではインプット(貢献)とアウトプット(成果)が釣り合っていない。この不公平状態はさらに不公平−有利状態と不公平−不利状態に分類できる。不公平−有利状態とはアウトプットがインプットより多い状態である。不公平−不利状態とはインプットがアウトプットより多い状態である。
B20.あいまいな表現を避ける。はっきり言い切るように書く。言い切るだけの自信のないことは、原則として書いてはいけない。
例:×・・・と言っても過言とは言えないと考えてよいのではないだろうか?
×・・・と思われる。
×・・・と言えよう。
○・・・である。
B21.表現をあいまいにする言葉をなるべく避ける。
例:「たぶん」、「ような」、「らしい」、「思われる」、「ほぼ」。
B22.可能な限り能動態を使う。受動態をなるべく避ける。
例:「・・・は〜と呼ばれる。」 → 「・・・を〜と呼ぶ。」
B23.可能な限り主語を明示する。
例:この Rothbart の説は後に退けられた。
→ Hamilton とその協力者たちは 1985 年以降の論文でこの Rothbart 説を退けた。
B24.主語と述語の対応に気をつける。
例:
× A. Rapoport の実験で目新しいのは、共財供給事態に集団間競争の要因を入れている。
○ A. Rapoport の実験で目新しいのは、公共財供給事態に集団間競争の要因を入れたことである。
B25.一つの文の中で主語が入れ替わってはならない。
例:×私は上記の仮説の検証に適した課題で実験を行い、その結果、仮説は検証された。
○私は上記の仮説の検証に適した課題で実験を行い、仮説を支持する結果を得た。
○私は上記の仮説の検証に適した課題で実験を行った。その実験の結果、仮説は支持された。
B26.主語と述語を近接させる。
例:×私は、・・・という条件の下で〜という現象が起こることに注目した。
○・・・という条件の下で〜という現象が起こることに私は注目した。
B27.解釈があいまいになることを避ける。
例:×A、B、Cの条件が満たされるとき、・・・
○A、B、Cの条件がすべて満たされるとき、・・・
○A、B、Cの条件の少なくとも一つが満たされるとき、・・・
○AとBがともに満たされるか、BとCがともに満たされるとき、・・・
B28.原則として指示代名詞(これ・それ・あれ・どれ・これら・それら)を使わない。「これ」と言う代わりに「この〜(名詞)」と言う。しかも「名詞」は先行詞(前の文の指示対象の名詞)と同じであるようにする。
例:× 〜とするのが Festinger の説である。これは・・・を意味する。
○ 〜とするのが Festinger の主張である。この主張は・・・を意味する。
× 以下でどれが正しいかを検討しよう。
○ 以下でどの仮説が正しいかを検討しよう。
B29.指示形容詞(この・その・あの・どの−国文法では連体詞)を使う際は指示対象をはっきりさせる。
例:×その表は・・・
○前頁の2番目の表は・・・
○表3−4は・・・
B30.接続詞の選択に注意する。なぜ「しかし」か、なぜ「したがって」か、等をよく考える。接続詞がなくてよい場合が多い。
B31.「が」や「であって」で無意味に文をつなぐことをしない。文章が間抜けになる。できるだけ短い文に分解する。
B32.文章を書く上で正確さを最優先する。正確さを求めるあまり文章がくどくなっても構わない。
B33.論文全体をとおして文体を統一する。
B34.気取らず、平易・簡潔な文章を旨とする。
B35.よほど教養のある者を除いて、文語調・漢文調で書いてはならない。どうせ無理である。
B36.「です・ます」調で書いてはならない。緊張感がそがれる。
B37.形容(動)詞・副詞の使用を少なくする。感動詞は原則として使わない。
B38.過度に感情的な表現を慎む。
B39.差別的表現をしないように気をつける。
例:・・・当直の外科医が担当する。彼は・・・
→ ・・・当直の外科医が担当する。その外科医は・・・
B40.時間がある限り書いた文章を読み返す。なくてよい語句を削除するとともに、長めの文を短くする。
C.表記法
原稿用紙
C1.横書きにする。
C2.手書きよりパソコン、ワープロのプリンタで印刷出力する方が好ましい。
C3.パソコン、ワープロで印刷出力する場合、以下にしたがう。
a.用紙はA4サイズ、レター・サイズ、ないし 10インチ(× 11インチ)用紙とする。
b.インクの色は黒を基調とする。
c.一頁の文字数を 800〜2000 字の範囲に収める。
d.具体的なレイアウトは機械の性能と各自の美意識に任せる。
e.通常の文章の文字は原則として全角とする。
f.アルファベット、算用数字は半角文字とする。漢数字、全角にした方が見栄えがする算用数字(第1、2番目など)は全角にする。
C4.手書きで原稿を清書する場合、以下にしたがう。
a.用紙はB5判の 400 字詰用紙、もしくは B4判の 800 字詰用紙とする。B4判−800 字の場合は二つ折りにして提出する。
b.黒か濃い青のインクで書く。鉛筆書きはいけない。
c.文字は一ますに一字づつ書く。
d.算用数字、アルファベットは一ますに二字ずつ書く。大文字のアルファベットは一ますに一字で書く。
C5.句読点(。、)、ピリオドとコンマ(.,)、かっこ類(「・[・{など)は一文字と考え、一ますを使う。
C6.以下を行頭に書いてはいけない。
a.。、・など。
b.々
c.!と?
d.かっこ類の受け 」 ) ] など
C7.かっこ類のおこし 「 ( [ などを行末に書いてはいけない。
用字・用語
C8.論文全体をとおして用語・用字を統一する。
C9.漢字、かな、送りがなは国語辞典に準拠する。
C10.専門用語以外は、漢字表記を常用漢字の範囲にとどめる。難しい漢字はひらがなで書く。
C11.手書きで清書する場合、略字使用を最少限にとどめる。
C12.以下の言葉はひらがなで書く。
及び、並びに、乃至、或る、或いは、即ち、則ち、但し、勿論、殊に、沢山の、色々の、〜する時に、〜である事は、〜と共に、〜に拘らず、〜と言うこと、出来る、我々、(私)達
C13.以下もひらがなで書くのが昨今の趨勢である。
初めて、再び、従って、各々、普通、他の、〜の通り、分かる、行う、始める・始まる、決める・決まる、覚える、私
C14.普及したものを除き、略語を使用しない。 例外:2SLS、ns、など。
C15.新造語をなるべく使用しない。使用する場合は正確に定義する。
C16.単位・量の記号、指標・統計量の記号にはなるべく慣用的記号を用いる。
C17.数字はなるべく算用数字とする。
C18.正確には漢数字で書くべきであっても、以下の場合は算用数字でもよい。
1つ2つ、3人、第4、5番目
C19.次の場合は漢数字で表記する。
a.名詞、副詞に含まれる数詞
例:一定、一方、一様分布、一気に
b.熟字に含まれる数詞
例:八百屋、三味線
c.概数を示す慣用的表現
例:何万人、数千円
d.固有名詞
例:一条通り、二重橋、三里塚、四日市
e.貨幣、化合物名
例:一万円札、六価クロム
f.漢字で書く習慣が強いもの
例:七五三、日本一・世界一
C20.中黒の点・は名詞を並列的に列挙するときに使う。
C21.「」(かぎ)は、会話文、引用文、強調したい語句、論文名を指すのに使う。
C22.『』(二重かぎ)は、書籍・雑誌などの刊行物名、映画・TVなどの作品名、「」の中の「」(例えば会話文の中の会話文)を指すのに使う。
C23.−(ハイフン)および〜(波ダッシュ)は数の幅を示すのに使う。
例:300〜500円、1か月に 2-3 回
C24.=(二重ハイフン)は等しい語句をつなぐときに使う。
注
C25.注は 末尾注(endnote)と脚注(footnote)に分かれる。何れか一方で統一する。
C26.末尾注は本文の末尾、もしくは各章の末尾にまとめて書く。本文全体、もしくは章ごとに通し番号をつける。
C27.脚注は各頁の下にまとめて記述する。脚注の番号も本文全体、もしくは章ごとの通し番号とする。
C28.一頁の文字数が多い場合(ワープロ使用時)は脚注が、一頁の文字数が少ない場合は末尾注が望ましい。
C29.本文に入れると叙述の流れを妨げる文章を注にする。
C30.出典を示すことを目的に注を使ってはならない(C50、C51、C54)。
C31.多くの場合、注は不要である。つけない方がよい。
文献リスト
C32.論文の本文の後に引用文献(references)のリストをつける。引用文献リストでは本文で引用したすべての文献を次の原則で配列する。
a.邦文欧文を問わず、著者名(姓が先、名が後)のアルファベット順にならべる。
b.同一著者による複数の文献は出版年の順にならべる。
c.同一著者、同一出版年の複数の文献には、出版年の後にa、b、c、・・・の記号をつけ、その記号の順にならべる。
例:○山×男 1988a. 「・・・」、・・・
○山×男 1988b. 「・・・」、・・・
C33.引用文献リストに書く文献情報の項目、および項目の記述順序は学問分野によって異なる。同じ分野でも雑誌・本によって異なる。以下に示す方式は可能な方式の一つである。
C34.邦文の著作(単行本)は引用文献リスト中に次の形式で表記する。
著者名 出版年. 『書名』、出版社名(補 助情報−もしあれば).
例:
木下是雄 1981.『理科系の作文技術』、中央公論社(中公新書).
富田軍二、小泉貞明、石館基 1975. 『科学論文のまとめ方と書き方』、朝倉書店.
C35.邦文の雑誌論文は引用文献リスト中に次の形式で表記する。
著者名 出版年. 「論文名」、『雑誌名』、巻、号、頁範囲.
例:
剣桃太郎 1987. 「赤池の情報指標によるカテゴリー合併の方法」、『行動計量学』、14、2、17-28.
大豪院邪鬼、伊達臣人 1988. 「スキーマの自己実現と認知的複雑性」、『社会心理学研究』、18、1、1-12.
C36.単行本に掲載された邦文論文は次の形式で表記する。
著者名 出版年. 「論文名」:編者名(編) 『書名』、出版社名(補助情報−もしあれ ば)、所収(頁範囲).
例:江田嶋平七 1990.「役割」:大坊郁夫、安藤清志、池田謙一(編)『社会心理学パースペクティヴ3』、誠信書房、所収(70-92頁).
C37.欧文の著作(単行本)は次の形式で表記する。
著者名 出版年. 書名. 出版社所在地:出版 社名.
例: Spence, J.T., & Helmreich, R.L. 1978. Masculinity and feminity:
Their psychological dimensions, correlates, and antecedents. Austin: Univ.
of Texas Press.
C38.欧文の雑誌論文は次の形式で表記する。
著者名 出版年. 論文名.雑誌名、巻、号、頁範囲.
例:Kalick, S.M., & Hamilton III, T.E. 1986. The matching hypothesis reexamined. Journal of Personality and
Social Psychology, 51, 4,
673-682.
C39.欧文の単行本に掲載された欧文論文は次の形式で表記する。
著者名 出版年 論文名 In 編者名(Ed./Eds.), 書名. 出版社所在地:出版社名、Pp.頁範囲.
例:Berscheid, E., & Walster, E. 1974. Physical attractiveness. In L.
Berkowitz (Ed.), Advances in Experimental social psychology(Vol.7). New
York: Academic Press, Pp.157-215.
C40.欧文の著作(単行本)の邦訳本は次の形式で表記する。ただし邦訳が日本で出版されていても、自分が参照したのが原本であるなら、邦訳本の情報を記す必要はない。
著者名(編者名) 出版年. 書名. 出版社所 在地:出版社名. 著者名(カタカナ) 本邦出 版年. 『書名』、訳者名(訳)、出版社名.
例:Milgram, S. 1974. Obedience to Authority. New York: Harper & Row. ミルグラム 1980. 『服従の心理』、岸田秀(訳)、河出書房新社
C41.欧文文献の場合、著者名は last name 以外をイニシャルで表示する。
C42.欧文文献の刊行物名(アルファベット)をイタリック体で表記する。手書きか、ワープロがイタリックの字体を持っていないときは、刊行物名にアンダーラインをつける。
例:Journal of
Personality, 31, 23-45.
Journal of
Personality, 31, 23-45.
C43.欧文文献の編者が一人なら、編者名(Ed.), とする。編者が複数なら、編者名(Eds.), である。
C44.姓の前につく de、van、von などの小文字で始まる語は姓の一部とみなす。しかし文献配列の順序はそれら小文字の語を省いて決める。
例:Richard von
Hertwig → von Hertwig, R. としてHの部に分類する。
C45.La、Mac、Mc など、姓の冒頭につく大文字で始まる文字列は姓の一部とみなす。配列順序もそれら冒頭の文字列を含めて決める。
例:William H.
McCarthy → McCarthy, W.H. としてMの部に分類する。
C46.著者名・編者名は、何人いても、省略してはならない。しかし本文中で引用するときは省略することができる(C53)。
C47.文献リスト中の文献数が 200 を越えない限り、雑誌名を略記してはならない。雑誌名を略記する場合は一般に通用している略記法にしたがう(例:Journal
of Personality and Social Psychology → JPSP)。また略記の凡例を文献リスト冒頭に載せる。
文献引用
C48.著者名[姓]と出版年が文献を指す。
例:White(1980)、井上・山本(1985)
C49.文献リスト中に同姓の著者が複数いる場合、姓(last name)と first name のイニシャル(邦文文献の場合は名)で文献を指す。
例:P. Brown
& Levinson(1978)
戸田正直(1967)
C50.著者名(出版年)を名詞(固有名詞)として使用できる。
例:Smith(1975) の仮説は・・・
C51.文献を挙示する場合は、かっこの中に著者名と出版年を記入する。複数の文献はセミコロン(;)でつなぐ。
例:Smith(1975) の仮説は別の実験課題を用いても再現されている(Cash,1981;
Gilman & Danet, 1979; Turnbull, 1982; 吉原, 1980)。つまり、・・・
C52.著者が3名以内の文献については著者名を省略してはならない。
例:品川・目黒・足立(1990)、Shaw, Brown
& Baxter(1969).
C53.著者名が4名以上の文献は、第1著者以外を「ら」で省略する。
例:大田ら(1989)、Kosugi ら(1978).
C54.引用した文献の特定の頁の記述であることを指すときは次の例にしたがう。
例:上式が示す指標は「情報の縮約によってモデルに生じたストレス」(中原,1979:114)を表している。・・・ →かっこの中の語句が中原(1979)の114頁の記述であることを示す。
C55.邦訳本の引用は次の例にしたがう。
例:(Festinger,
1965) − 頁数を記さぬ限り邦訳本を参照したことを明記する必要はない。
(Festinger,
1965, 邦訳:213) − 邦訳本の213頁を指す。
C56.まとまった長い文章をそのまま引用する場合は次の作法にしたがう。
a.引用記入箇所の前後を一行づつ開ける。
b.引用記入箇所の左右をそれぞれ数文字分内側に下げる。
c.可能なら本文より小さい文字を使う。
d.出典を必ず明記する。
C57. 400 字より長い文章をそのまま引用してはならない。
C58.そのまま引用する文章が書いている論文全体の2割を越えることは許されない。誰の論文か分からなくなる。
C59.そもそも原文をそのまま引用するのは望ましくない。可能な限り自分の文章に翻訳し、原文の意味を要約的に記述すべきだ。
図と表
C60.図(figures)は概念図、グラフ、図画、地図、写真を含む。写真を図とは別の体系と考えてもよい。この文書の読者が利用する可能性が高いのは概念図とグラフである。
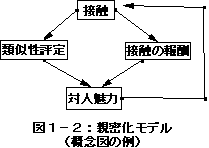
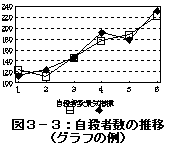
C61.概念図、グラフの作成にはプレゼンテーション用ソフト(Lotus
Freelance、Harvard Graphics など)を利用すると便利である。グラフを作るだけならグラフ機能のある表計算ソフト(Lotus 1-2-3、アシスト・カルクなど)が時間を節約してくれる。
C62.図に通し番号をつける。
例:図2−2 = 第2章の2番目の図
C63.図の通し番号および表題を図の下につける。
C64.表(tables)では数字や文字を体系的に表記する。
C65.罫線が多くなり過ぎないよう注意する。表に縦の罫線を使わないのが当世の流儀である。
表3−2:接触度数の回帰分析
━━━━━━━━━━━━━━━━
要因 β t値
────────────────
近接性 .233 1.53
接触期間 .489 3.12*
態度の類似性 1.245 4.38**
階層の類似性 .567 2.97*
━━━━━━━━━━━━━━━━
* P<.05, ** p<.01
C66.表には通し番号をつける。
例:表4−3 = 第4章の3番目の表
C67.表の通し番号および表題を表の上につける。
C68.必要に応じて、表に記した略記号や統計量などの意味を説明する注をつける。注の対象の右上に識別記号(*、**、a、b、など)をつける。そして注を表の下部に書く。上記の例を参照せよ。
C69.生のデータを本文中に表として提示すべきではない。生のデータを収録してよいのは末尾の付録だけである。
C70.一頁の文字数が少ない場合(例えば400字)、一つの図ないし表に一頁を費やす。一頁の文字数が多く、作図・作表機能のあるワープロなどを使っている場合は、図や表を文章中に埋め込んでもよい。
C71.図と表を論文末尾に一括して収録し、次例の方式で図や表を置く箇所を
指定してもよい。
例:
・・・・・・・・・・・・
・・・・(文章)・・・・
─────────
図3−2
─────────
・・・・(文章)・・・・
C72.同じデータを図と表の両方で示すことは原則として許されない。
C73.次の何れかの場合は図や表の下部に出典を明記する。
a.他の文献の図や表をそのまま利用する場合。
b.他の文献にある資料を加工して図や表を作成した場合。
例:Atkinson(1979)の Table
5(p.284) から作成。
引用文献
木下是雄 1981. 『理科系の作文技術』、中央公論社(中公新書).
木下是雄 1990. 『レポートの組み立て方』、筑摩書房.
永山嘉昭(編) 1992. 『文章・表現200の鉄則』、日経BP社.
埼玉大学教養学部地理学研究室 1987. 『卒業論文の書き方』、未刊行.
田中潔 1983. 『実用的な科学論文の書き方』、裳華房.
付録 表紙の問題の解答
Q1.大気中二酸化炭素の増加による気象変化と水資源への影響
[田中(1983:12)より]
Q2.1.1か月に2-3回(又は二三回)、2.数十人から数百人、3.300〜400人(又は三四百人)、
4.千円札、 5.十二指腸、6.第2四半期、 7.ハツカネズミ [田中(1983:34)より]
Q3.1.すらっとした脚がきれいな黒人娘、
2.すらっとした脚を持つ美人の黒人娘、
3.背がすらっとし、脚が美しい黒人娘、
4.すらっとした脚がきれいな黒人が生んだ娘、
5.すらっとした脚を持つ美人の黒人が生んだ娘、
6.背がすらっとし脚が美しい黒人が生んだ娘、
7.脚が美しい黒人が生んだすらっとした娘、
8.美人の黒人が生んだすらっとした脚の娘、
の8通り。
[田中(1983:44)より]