社会心理学概説A講義プリント
2000.12.11
D.群集過程
D.1.概念
集合現象(collective phenomena)、群集行動(crowd behavior)。
集合行動(collective behaviors):
多くの人々の間で生じる、自発的で非構造的な、思考・感情・行動の様式
2つの見方
1.集合行動 = 群集行動 + 社会運動
2.集合行動と社会運動は別
群集(crowds):相互の行動に影響が生じ合うほど近接している近接している
人々の集団
☆ 群集行動の諸形態(分類)
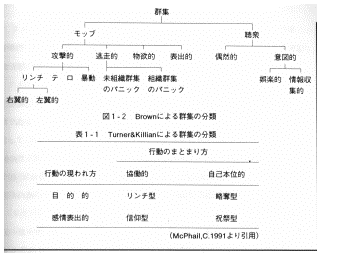
その他の形態
○流言(rumors):急速に生じる、検証困難な情報の伝達。
重要であるにもかかわらず不確かな事象について理解しようとする、
人々の集合的な試み
不安、緊張 ---> 人々は状況を理解しリアリティを構成しようとする。
緊張が高いほど人は繰り返す。
周辺的で地位が低い人が流言に加わる、とする説(Koenig, 1982,1985)
(流言の期間だけは注目を受ける。)
○ファッションとファド
ファッション(fashion):短期間持続し、社会に広く受け入れられる行動様式
例:服装、車、家の様式
ファド(fad):短期間持続し、社会の一部にだけ受け入れられる行動様式
例:遊び、ゲーム、ダンスステップ、タレント、仲間言葉
クレイズ(crazes):fadの高揚した形態
例:土地投機
○マス・ヒステリア(mass histeria) 〜 集団ヒステリー
ヒステリー感染(hysterical contagion)
ストレス、不満による。
例:単調労働の工場−従業員が突如、連鎖的に、吐き気、頭痛、呼吸困難などの
症状を訴える。(低賃金の女子単純労働者に多い。)仮病ではない。
例:dancing mania − 14世紀後半のドイツ(黒死病の恐れ)
☆ 群集行動の古典的理論(社会学)
群集成員が同じような行動をとることに対する説明
1.感染理論(Contagion Theory) − Le Bon (1896) など。
「群集心理(crowd mind)」
・群集の中で感情、態度、行動が急速に広まり、無批判に受け入れられる。
・模倣、暗示性(suggestibility)、循環反応(circular reaction) の重要性。
2.収斂理論(Convergence Theory) − Cantril(1941) など。
・同じ傾向を持つ人が集まって来る。
Cantril(1941):リンチへの参加者は、犯罪歴のある、下層の人が多い。
3.創発的規範理論(Emergent-Norm Theory)− Turner & Killian(1972)など。
・通常の規範が存在しない群集状況で、群集成員は適切な行動を指示する
新たな規範を作り出す。
D.2.没個人化(deindividuation)
没個性化
群集の中で個人のアイデンティティが消滅すること。
群集の中にいると、人は、一人では行わないような行動をとることがある。
(行動の抑制がきかなくなる。)
☆ 没個人化の徴候
1.自分の行動への抑制の低下(衝動的行動)
2.身近の手がかりや現在の感情に流されやすくなる。
3.合理的思考の低下。
4.他者による評価への関心の低下。
☆ 没個人化が生じる条件
1.集団内の匿名性(個人が識別されない)。例:暗い、人数が多い。
2.生理的喚起(興奮)の増大。
3.外部事象への注意の集中。
4.集団の一体感。
Diener 説:以上の条件が自己意識(自己を監視する作用)を低下させ、没個人化を生む。
[研究例]
Singer ら(1965) の実験
女性の被験者にポルノに関して討論することを求める。
匿名条件−被験者はみな同じコートを着ている。
識別条件−被験者は各々別の服を着、名札を付けている。
結果:匿名条件の被験者の方がひわいな言葉を使いやすい。
Johnson & Downing(1979) の実験
被験者(女性)は他者に与える電気ショックの水準を変更する機会を与えら
れる。
条件
1.KKK条件−KKK団員の服装をする。(服装=状況的手がかり)
看護婦条件−看護婦の服装をする。
2.匿名条件 −被験者は匿名的。
識別条件 −名前が分かる。
結果
1.被験者の行動はは直接的な手がかり(服装)に影響された。
KKK条件:ショック水準を上げる。
看護婦条件:ショック水準を下げる。
2.服装による差は匿名条件でより大きい。
(没個人化傾向)
Mann(1981)の分析:飛び降り自殺をけしかける群集(baiting crowds)
飛び降り自殺騒ぎの新聞記事(1964-1979)のうち、見物の群集に言及された
記事を調べる。
New York Times - 15ケース。
Chicago Tribune - 6ケース。
計21ケースのうち、群集が自殺をけしかけたのは10ケース。
群集が自殺をけしかけたケースの共通点。
群集の規模が大きい(300人以上) → 匿名性
夜 - → 匿名性
6〜12階。
騒ぎが長い。 - →注意の集中
6−9月(暑い、不快)。
D.3.集団による攻撃
☆ 集団による攻撃(Group Aggression)の促進要因
・生理的喚起+「怒り」のラベルづけ
・武器効果(Berkowitz & LePage, 1967)
相手が武器を持つ → 攻撃を誘発
・攻撃行動のモデリング
・内集団を均質的と見る傾向
(assumed similarity, the false
consensus effect)
自分が所属する他の集団成員が自分と同じ態度を持つと推論しやすい。
・外集団を均質と見る傾向(out-group homogeneity)
外集団は均質的であり、自分たちとは異なる、と誇張して認知する傾向。
・集団極化
・没個人化(D.2.)
・創発的規範
憎む相手と接触する局面では相手への攻撃を「適切な行動」とする規範が
生じやすい。
☆ 攻撃に対する生理的要因
・生理的喚起(興奮)
生理的喚起が高いと攻撃しやすい。ただし次の場合。
(1) 攻撃が優勢反応である。
(2) 生理的喚起が「怒り」だとラベル付けされる。
・性的な興奮:研究によって結果は異なる。大ざっぱな傾向としては、
性的な興奮が中くらい(ヌードを見る) − 攻撃は抑制される。
性的な興奮が高い(露骨なポルノ) − 攻撃が高まる。
・アルコール、マリファナ
アルコール ― 少量なら攻撃低下。多量なら攻撃増大。
マリファナ ― 攻撃低下。
・気温
中くらいの暑さ − 攻撃が最も高まる。
暑過ぎる場合 − 攻撃低下。
Baron & Ransberger(1978):米、1967-1971 の102の暴動の研究
"Long, hot summer"
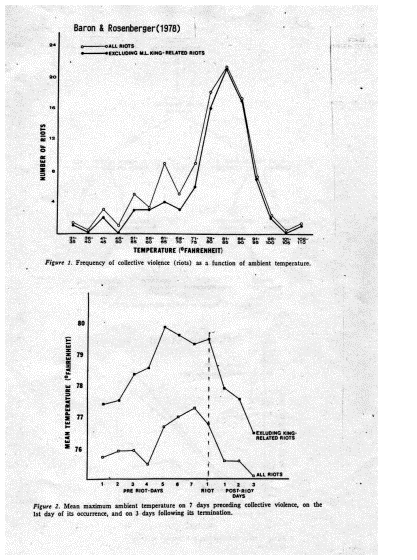
・暴動が多いのは、80F°台。それ以上高いと暴動は低下する。
・気温は暴動の数日前に高く、暴動の終息とともに下がる(次の Figure 1, 2)。
|
[以上] |