社会心理学概説A講義プリント
2001.01.15
D.群集過程(続き)
D.4.パニック(panic):逃避的な群集行動
パニックの問題
1.個人の非合理的な行動(非計画的、衝動的行動)
2.混雑現象による問題の増幅
パニックを生じさせる要因
1.合理的要因
逃げ遅れるとひどいことになるほど混乱が生じやすい。
囚人のジレンマのような利得構造
2.情動的要因
恐怖によって、融通性の低下、退行、合理的な思考の欠如が生じる。
Mintz(1951) の実験
15〜21人の被験者集団の実験。
被験者は、ひもを早く瓶から抜くことを求められる。
しかし、一度に一人しか出られない。
結果
1.報酬構造が混雑を生じさせる。
・ 抜け出すと報酬が得られる場合、混雑が生じやすい。
・ 瓶に水が入る。cone がぬれると罰金が科される。
→ 混雑がひどくなる。
2.被験者間の話合いを導入すると、混雑は低下する。
3.被験者に協力的な「構え」を持たせる(集団の得点を上げるように教示)。
→ 混雑は著しく低下する。
Mintz(1951) の実験への批判
現実性があるか?
罰金が低額である。
Kelley ら(1965)の実験
Sは仕切りで隔離される。
装置 − Sの位置と他のSsの位置をライトが示す。
時間内に逃げられなければ電気ショックがある。
スイッチを押す = 逃避の試み。しかし一度に一人しか逃げられない。
実験 1
条件:脅威 − 高/中/低(ショック無し)
集団規模 − 4/5/6/7人
性別 − 男/女
Sには2つの反応が可能 = 逃避の試み / 待つ。
与えられた時間
4人集団−24秒。5人−30秒。6人−36秒。7人−42秒。
タイマー:赤い水がある瓶から別の瓶に流れる。
結果
1.逃避に成功する割合: 男性 > 女性。(p < .025)
2.大集団ほど避難に失敗する。
4人 5人 6人 7人
成功率 77% 57% 31% 49%[例外]
3.脅威が高いほど成功率が低い。
7人集団で成功率が高かった理由 − 7人集団では、瓶の水が多いため、
時間が十分あると思われたかも知れない。
実験 2
時間の経過を音で示す。
全てのSsに実験1の中脅威を使う。
条件: 集団規模[4〜7人]×性別
結果:逃避の成功率は、
1.男性 > 女性。
2.4、5人集団 > 6、7人集団。
成功率 4人 5人 6人 7人
48% 50% 22% 21%
実験 3:7人集団で実験。
条件:性別
Sに可能な反応の数
2反応条件:待つ、避難の試み。
3反応条件:+ 「待つつもり」 − 他のSsにも分かる。
結果:避難の成功率は、
1.男女差無し。
2.3反応条件 > 2反応条件。
全体の結論
1.脅威の大きさ → 混雑を生む。[Mintz(1951) と同じ。]
2.集団規模が大きい → 混雑を生む。
3.信頼感を与える反応の存在 → 混雑を緩和。
D.5.流言(rumor)
急速に生じる、検証困難な情報の伝達
「デマ」との相違: デマゴギー、意図的な扇動
D.5.1.発生原因
・オルポートとポストマン[Allport & Postman, 1947]
流言の強度 = f(問題への人々の関心×問題の曖昧さ)
(速さ、広がり)
・ロスノウ[Rosnow, ]
・信じやすさ ←→ 批判的感受性
・情報に接したときの心理状態:恐怖、不安
Morris ら(1976)の実験:恐怖のストレスの下で情報追求行動が生じやすい。
4〜6名の被験者の集団が「性的態度」に関する実験に参加する。
1.恐怖条件:部屋に電気ショックの機械が置いてある。
「電気ショックと性的刺激に対する生理的反応の研究」をす
ると被験者に言う。
2.不安条件:部屋に避妊具、ポルノ、などが置いてある。
3.統制条件:どんな研究をするかは言わない。
待ち時間中の被験者の行動を観察する。
結果:恐怖条件で、
・言語的な情報追求行動が多い。
(何が起こるかを他者にたずねる、など。)
・集団凝集性が高まる。
Jaeger ら(1980)の実験
Ss:大学の授業に出席している学生
手続き:
・性格検査により、事前に出席者の不安を測定しておく。
・授業中に教授(高権威条件)/学生(低権威条件)が次のように発言
「マリファナを吸っていた学生がいるという噂があった。事情を知っている者はいるか?」
・ある学生(サクラ)が次のように答える。
高信用条件:「あり得る。」
低信用条件:「デタラメな話だ。」
・1週間後に、マリファナの噂を人に話したかどうかを調査
結果
1.噂を他人に伝える傾向は 高不安者 > 低不安者
2. 噂を他人に伝える傾向は 高信用条件 > 低信用条件
3.高権威条件(情報源の権威が高い)では、Sの不安にかかわらず噂の伝達がおきる。
低権威条件では、高不安者が噂を伝達しやすい。
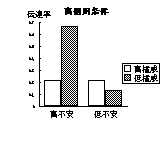
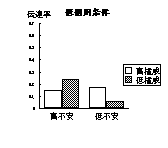
D.5.2.流言の伝播過程
Allport & Postman(1947)の実験:流言の伝播過程で情報は変容する。
実験刺激 − 次頁、左図
図を見せられた人が、見ていない人に図の内容を伝える。
伝えられた人は別の人(図を見ていない)に伝える。・・・
結果:次の3つの傾向が観察された。
1.平均化(leveling):簡略化される。思い出したり伝えるのが容易になる。
2.強調化(sharpening):特定の部分が強調される。(平均化と同時進行)
平均化と強調化の例−「果物を盗んだ少年がいて、警官が後を追っている。」
3.同化(assimilation):伝えられる内容が伝える人の態度・関心・期待に一致するようになる。
例−女性は店のドレスを伝えることが多い。
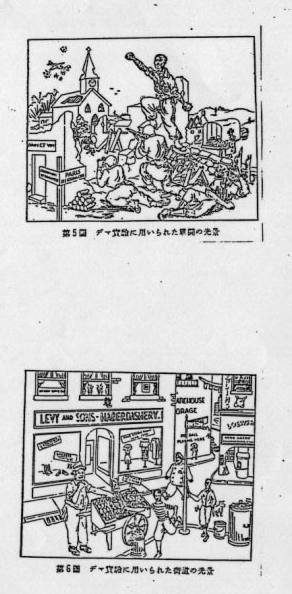
情報は人々のスキーマ[図式]に従って変容する。 (記憶に対するスキーマの影響)
Bartlett(1932)の実験:図形や絵文字をリレー式に再生させる。 次頁、右図
人は既存のスキーマに当てはめて図形を記憶しようとする。
そのため、伝えられる図形は、伝播の過程で分かりやすいスキーマに従ったものとなる。
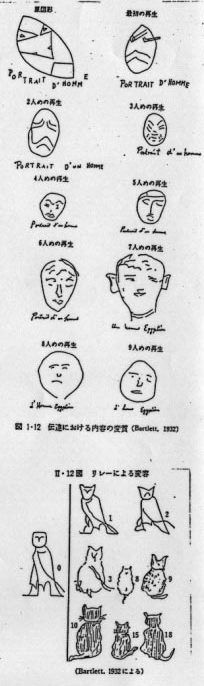
D.6.混み合い(crowding)
D.6.1.空間行動(spatial
behavior) 〜 個人的空間(personal space)となわばり行動(territoriality)
☆ personal space 説 Sommer ら。
(proxemics, Hall)
personal space − 他者の侵入が脅威となる、個人の回りの空間
接近 → 不快。脅威・怒りを感じる。
Sommer らの実験−サクラが接近するほど、相手はその場を早く立ち去る。
攻撃的な人ほど、広い個人的空間を要する(特に背後)。Kinzel(1970)
☆ なわばり行動
3種類のなわばり(Altman,1975)
第1次的なわばり 例:自宅
第2次的なわばり 例:教室の自分の席
公的なわばり 例:気に入った公園
安心感、統制感覚は第1次的なわばりで最も高く、公的なわばりで最も低い。
Home Court Advantage − スポーツ、交渉
(ニワトリ、魚も同様 − the prior residence 効果)
家庭内のなわばり − 夫のなわばり=居間、ガレージ、妻のなわばり=台所
D.6.2.混み合い(crowding) → 空間行動上の障害
☆ 動物のデータ
込み合った状況下のネズミ → behavioral sink (Calhoun,1962)
・不可解な攻撃行動、あるいは、
・消極的になって閉じこもる(withdrawal)
[例]
・母親ネズミが子供に注意しなくなる。→子供の死亡率、大
・通過儀礼を経ずに性的行動に走る、もしくは、性的行動から全く遠ざかる。
・ストレス症状
・争いが高まる。(Southwick, 1955)
☆ 人間の場合
混み合い → 目標の阻害 → 混み合いによる症状
・ストレス
・無力感
・引きこもり(withdrawal)
他者との接触を回避
例:eye-contact を避ける。
・攻撃
☆ 課題達成への影響
Freedman ら(1971,72)
混み合いは知的課題(例:文字のリストから単語を作る)の達成を阻害しない。
→ 混み合い自体はストレス因(stressor)にはならない。
しかし、ストレス下で達成の阻害が生じる課題を使った実験は、混み合いがストレス因になることを示す。
Paulusら(1976):混み合い下で迷路課題の達成が低下。
Evans(1975):混み合い下では2次的課題(テープの話に注意する)達成が低下。
など。
達成の阻害は、他者との接触を要する課題で大きくなる。
(Heller ら、1977)
☆ 利他的行動への影響
Steblay(1987):35の援助研究のメタ分析。援助行動は小都市で生じやすい。
Bickman ら(1973):込み合ったところではロスト・レターを投函する人が少ない。
Cohen & Spacapan(1978):コンタクト・レンズ探しへの援助。
込み合ったショッピング・モールでは生じにくい。
など。
混み合い → 注意の過重負荷 → 他者への非関与
☆ 攻撃:混み合いは攻撃と怒りの情動を高める。
喧嘩が生じやすくなる。
Booth & Edwards(1975):トロントの白人世帯の調査
・主観的に世帯が狭いと愛情が低下する。
・主観的に世帯が狭いと夫婦喧嘩が多くなる。
・部屋数が少ないと子供がぶたれやすい。
攻撃か閉じこもりか?
・資源(オモチャなど)の希少性 → 攻撃
・男性:混み合いによって攻撃しやすい。
☆ 生理的反応
Middlemist ら(1976):込み合った男子トイレでは、おしっこの出が遅れる。
おしっこ:ストレスによる生理的喚起で、出が遅れる。
血圧、心拍数も同様
Levy & Herzog(1974):込み合った地区では心臓病での死亡率が高い。
Paulus ら(1978):監獄の研究。監獄が込み合っている時期には、循環器系の疾病による死亡率が高い。
☆ 子供の研究
Rodin(1976):込み合った住宅に住む子供は、根気がない。
(環境に対する統制感がない。学習性無気力)
☆ 媒介変数としての統制感覚
混み合いの原因を自分で除去できる、という感覚(統制感覚)
→ 混み合いの負の効果を低下させる。
Rodin ら(1978):エレヴェータの混み合い。
スイッチのそばにいる(いつでも出られる)Sは、混み合い感が低い。
D.6.3.生態学的心理学(Ecological
Psychology)
〜 the theory of manning
Baker, R.G. & Gump, P.V.
(1964) Big school, small school. Stanford, CA: Stanford Univ. Press.
Wicker, A.W. (1979) An introduction to ecological
psychology. Belmont, CA:
Wadsworth.
行動場面(behavior settings) 〜 イヴェント、定常的社会活動の場、など。
・具体的に時間(帯)・場所を指定できる。
・2つの構成要素 (1) 人、(2) 器材(例:椅子、タイプライター)
・プログラムがある−相互作用の流れを規定。
・構成要素間の調和(synomorphy)
・地位の体系 例:代表者、客、・・・
・人員が代替可能
・場面の自己制御的性格
など。
例:○○ミーティング、運動競技会、カウンセリング室
Barker らの理論
人員不足(undermanning)の効果
1.場面のプログラムを実行する個人の活動がより活発になる。
2.個人は責任ある地位を引き受ける。
3.場面にとっての重要性を個人が自覚する。
Barker & Gump(1964):カンサス州の高校の調査
・生徒数の多い高校では、生徒数ほどには行動場面が多くならない。
・小さい高校では生徒の課外活動への参加が活発になる。
─────────────────────────────
参加の測度 小さい高校平均 大きい高校平均
─────────────────────────────
参加場面総数 19.4
18.4
参加場面の種類 6.5
5.4
責任ある地位にある場面数 8.7
3.5
中心的地位にある場面数 3.6
0.6
責任ある地位の種類 3.7
1.6
─────────────────────────────
[以上]