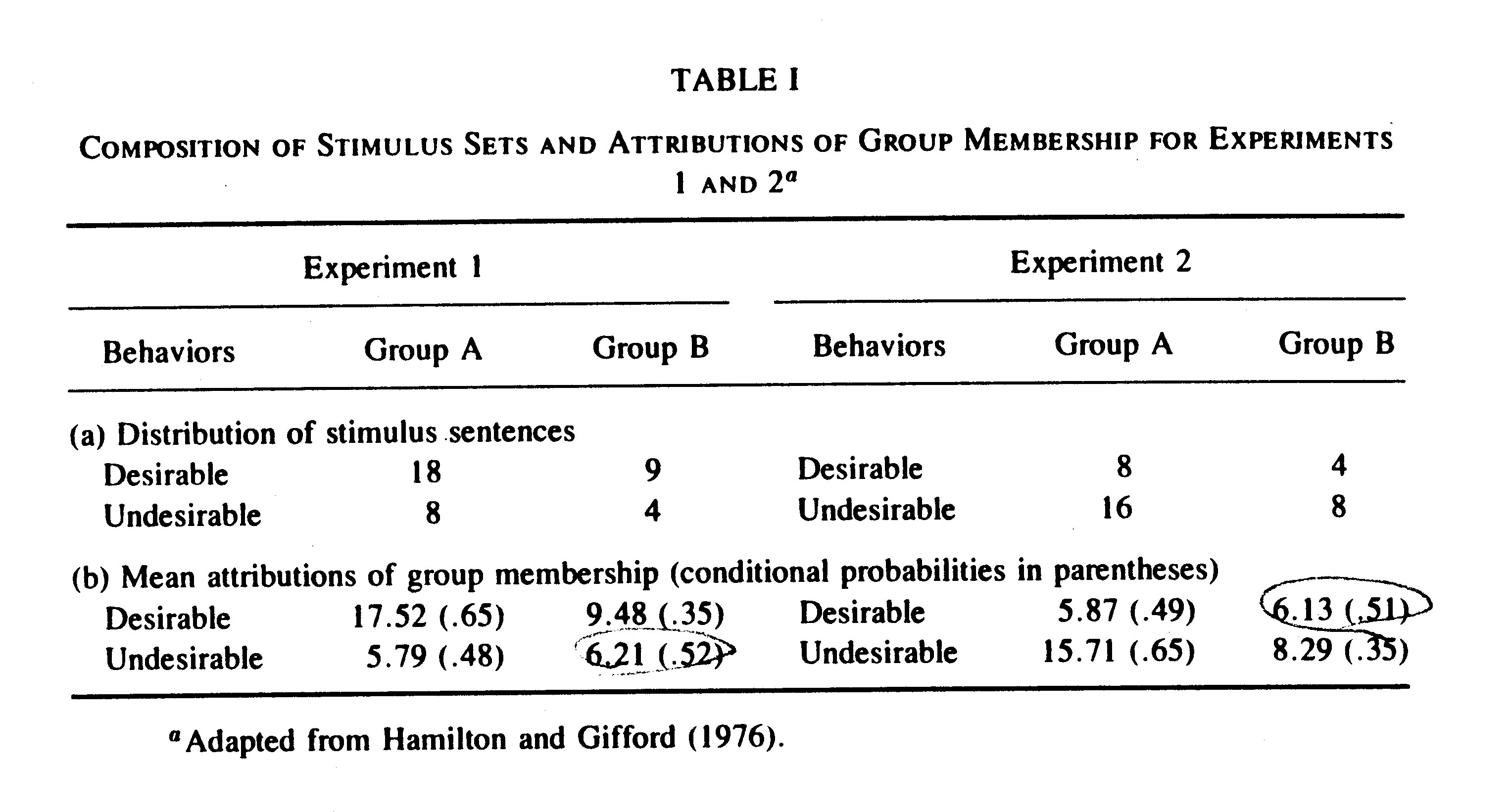
社会心理学入門A(a)
2000.06.26
高木英至
B.3 集団の認知
B.3.1 誤った関連づけ
Ssに人の行動の多数の事例を示して、後に思い出させる。
事例 − 大集団/小集団、 多数派事例/少数派事例(例:望ましい、望ましくない行動)
→ 小集団の少数派事例が過大評価される。
(Hamilton らの実験)
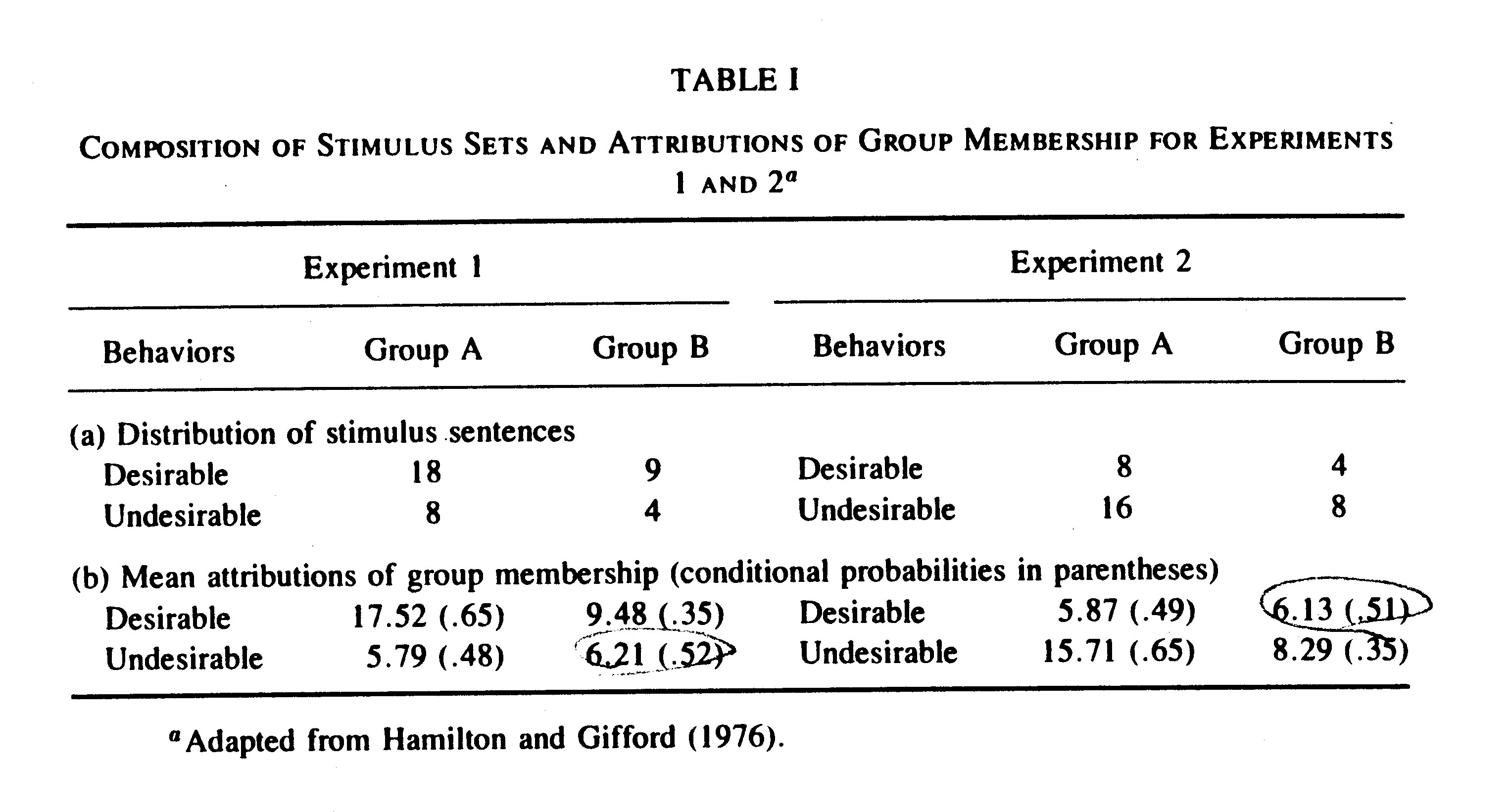
説明
1.2重の目立ちやすさ
(Hamilton ら)
「小集団」、「少数派」は目立つ。
→ 小集団の少数派事例は2重に目立ちやすいので、再生されやすい。
2.学習試行の相違
(Fiedler)
小集団の事例は少ないので、学習が不十分
→ 小集団に関する情報があいまいになる
→ 中間的評価への回帰が生じる。
B.3.2. 内集団/外集団
内集団 (in-groups)/外集団(out-groups) − 社会学者のサムナー(Sumner, G.W.、『フォークウェイズ』)
伝統的な見解:目標競合、競争 → ・内集団の類似性の誇張、集団凝集性
(
Sherif ら,1961) ・外集団成員=均質、と見る。内集団との差を誇張。
その後の研究:目標競合がなくても内輪びいき(
in-group favoritism)が生じる。(
Tajfel らの最小集団パラダイム)
(1)
外集団成員を均質と見る傾向
【例】
・1人の意見を集団全体に一般化する傾向は、内集団より外集団
(他大学)に対して高い。(Quattrone & Jones,1980)
・女子学生。ファッションや学習態度に関し、自分の寮成員にはヴァラエティがあると思う。しかしライバル寮の成員は均質的だと思う。(
Park & Rothbart,1982)
・パーソナリティ、行動の特徴の違いを内集団成員に対してより知覚しやすい。
(Jones et al,1982; Park & Rothbart,1982)
・顔を正確に認識する能力は、自己の人種に対して高い。この傾向は年齢とともに高まる。
(Chanceら,1982)
Linville ら (1989) の実験

(2)
内集団びいき傾向
内集団の認知=道徳的、平和愛好、従順
外集団の認知=その逆
→ 相互的なステレオタイプ 〜 ミラー・イメージ
(mirror image)説
・「究極の帰属エラー」
─────────────────────────
外集団成員 内集団成員
─────────────────────────
悪い行為 パーソナリティ 状況要因
(内的、安定的) (外的、一時的)
良い行為 状況要因 パーソナリティ
─────────────────────────
ただし、次の傾向があるとする説がある(Marques
ら)。
「黒い羊効果」:内集団の劣った成員を外集団の劣った成員よりも低く評価し、内集団の優れた成員を外集団の優れた成員よりも高く評価する。
○社会的アイデンティティ理論
(タジフェル、Tajfel)
(参考文献:ホッグ、アブラムス 『社会的アイデンティティ理論』 北大路書房)
1.カテゴリーによる単純化した認知
2.
個人はカテゴリー成員性を自分の社会的アイデンティティに取り入れる。
→ 所属集団の質・達成はわれわれの
self-esteem の重要な源泉
→ 認知・行動における内集団びいき
《分配における偏り》
・分配における内集団偏向
(Tajfel,1982)、内集団/外集団の差を最大化
・集団間の敵意、抗議運動支持の予測には、個人の
deprivation より自己の集団の relative deprivation の方が重要。(Tripathi & Srivastava,1981; Guimond &
Dube-Simard,1983)
[以上]