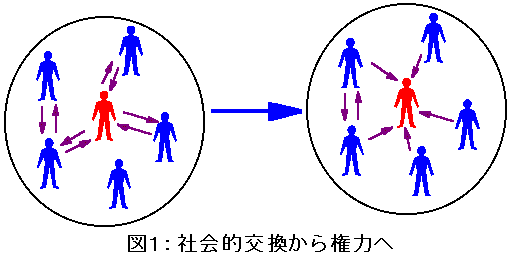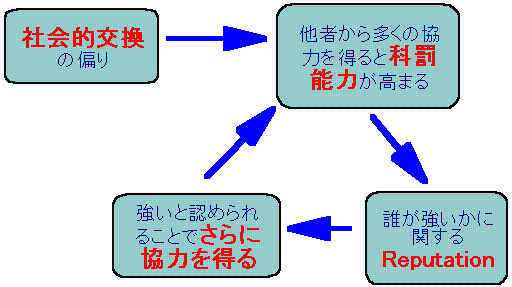[要約]本稿は権力発生の一経路を計算モデルによって検討する.他者に罰を科せる条件下で仮想のエージェントに協力の交換をさせるとき,交換から生じる「強さ」の偏りが交換の流れに作用し,協力を過大受領する「権力者」を発生させる.このアイディアが成り立ち得ることを計算実験で示すとともに,同モデルの問題点を議論する.(1)
1.計算モデルによる権力発生の検討
権力ないし社会的勢力は社会科学の最重要概念の1つである.社会には普遍的に権力が存在する.社会や集団の構造はほとんど常に,権力構造として特徴づけることができる.しかしその権力がなぜ存在し得るか,どのように発生するかについては,理論的にはあいまいである. 本稿が問題にするのは,権力の発生を説明する計算モデルの可能性である.
1.1.理論としての計算モデル
理論ないし説明モデルには3種類がある(Ostrom, 1988).第1は自然言語で記述した言語モデル,第2は数理モデル,第3はコンピュータのコードで記述された計算モデル(computational models)ないしコンピュータシミュレーションモデルである.
社会科学を含め「文系」の領域では元来,理論(モデル)は言語モデルとして記述されて来た.経済学者を除けば,社会科学の理論家はややもすれば,文献解読や文献解読に基づく思索を生業としてきた.データ分析に計量モデルを用いるとしても,理論自体は言語モデルとして表現することが多かった.経済学を別にして,社会科学における数理モデルの導入は限定的だった.社会学や政治学で数理モデルとして成功したのは,大半が(ゲーム理論を含めた)経済学の手法を導入した領域だった.
社会科学が言語モデルを用いるのはむろん自然な流れである.その理由には少なくとも次の2つがあるだろう.第1に,社会科学の「理論」がしばしば,前提から一定の帰結を導くような本来の理論ではなく,現実を記述するカテゴリー(群)に過ぎなかったことである.カテゴリーを自然言語以外で表現することには固有の意味はほとんどなかったはずである.第2に,社会科学がその議論の基礎とする人間行動のメカニズムが多分に「質的」であり,通常の数学的概念による表現になじみにくかった点をあげることができる.
しかし言語モデルには厳密性において欠点がある.第1に,モデルの論理的一貫性を確認することが言語モデルは不得意なことである.自然言語の操作は論理的矛盾を自ずと導くものではない.この点はモデルが複雑になるほど妥当する.第2は,言語モデルでは背後の暗黙の仮定が隠れたままになりやすいことである.第3に,モデルがどれほどの含意(implication)を持つかを評価することも難しい.われわれはモデルが導きたい帰結や含意を導けたなら,それ以上の操作をしないだろう.しかしモデルは,説明したい効果とともに説明したくない効果(つまり妥当性が期待できない結論)を含意しているかも知れない.
これらの言語モデルの欠陥に対処できるのは数理モデルと計算モデルである.両者ともモデル内の論理的矛盾を識別しやすく,モデル構成者に仮定を明示することを強制し,いろんな側面の帰結を導くことを得意としている.
ただし両者は同じ性格の存在ではない.計算モデルには数理モデルに明らかに劣る点がある.数理モデルが一定の結論を証明するものであるのに対し,計算モデルは証明をしない.sensitivity analysis はこの問題に対処する有力な方法である.が,原則として計算モデルにできることは「例を出す」ことだけである.つまり計算モデルは数理モデルに比べて厳密性,一般性に限界を持っている.
しかし計算モデルには数理モデルにはない利点もある(e.g.,Taber & Timpone, 1996).筆者が考える利点の第1はモデル構成の容易さである.計算モデルは要素的なステップの集積からなっており,個々のステップの構成は比較的やさしい.第2は特に,言語的アイディアをモデルに移植することが容易な点である.例えば個々のステップは if 〜 then ルールなど,自然言語の発想に近い演算で構成することができる.また,計算機向けのビット列コーディングなどで「質的」な属性を表現することに優れることである.特に人間行動をモデル化する場合はこの点が大きな助けになる.第3はモデルの融通性,柔軟性である.例えばいったん構成したモデルの改変や条件追加などは一般に容易である.
計算モデルはその限界にもかかわらず利点によって,多くの利用者を獲得しつつある.
1.2.人工社会の課題
社会科学における計算モデルは通常,次のように構成される.複数のエージェント(行為者)を仮定し,そのエージェントの行動ルールなどローカルなルールを前提としてエージェント間の相互作用を導くようなモデルである.エージェント間の相互作用の総体は計算機の中の仮想の社会,すなわち人工社会(artificial societies)と呼ぶことができる(Epstein & Axtell, 1996).人工社会に基づく研究の課題は,ローカル/マイクロなルール(エージェントのレヴェルのルール)から社会のグローバル/マクロなルール(社会構造,社会秩序)を導出することにある.
社会科学の計算モデルの中に「進化型のモデル」と呼び得る形式がある. 進化型のモデルとは進化ゲームの形式を備えた計算モデルを指す.すなわち,エージェントの行動ルール(しばしば戦略,遺伝子と呼ぶ)が相互作用のエージェントに対する結果に応じて変化し,エージェント間の戦略分布が変化(進化)する,というモデルである.進化型のモデルは結果に応じてエージェントの行動ルールを変化させるルール(進化ルール)を組み込んでいる.進化は生殖再生産に基づいて生じてもよい(良い結果を得たエージェントが自己の遺伝子をコピィした子孫を多く残し,良い結果を残せなかったエージェントの遺伝子は淘汰される).あるいは,観察学習によって生じてもよい(悪い結果を得たエージェントが良い結果を得たエージェントの戦略を学習する).進化型のモデル以外は便宜のため,「単純推論型のモデル」と呼んでおこう.
注意すべきは,エージェントの行動ルールの組が社会の状態を表現する点である. 行動ルールの組とは,エージェントiの行動ルールをaiとしたときの,
a=(a1,a2,・・・,an), ただしnはエージェント数
である.あるいは,行動ルールの組におけるある規則性が,社会構造ないし社会秩序を表している.
進化型のモデルが単純推論型と異なるのは,単純推論型では与件として固定されるエージェントの行動ルールや社会の構造が内生変数となっていることである.このことは,進化型モデルから生み出される人工社会が「自己組織的」な性格を帯びていることを意味する. 同時に,いい換えれば,シミュレーションのパラメータ(の少なくとも一部)をモデル自体の作動に任せることを意味している.
進化型のモデルは社会の状態を進化的均衡,ないし動的均衡(Thomas, 1984)として説明しようとする.つまり原則としてエージェントは自由に自らの存在(行動ルール)を変えられると仮定した上で,エージェントの存在したがって社会の状態が行き着く均衡を求めようとする.進化型モデルから予測される均衡とは,マイクロなルールから生まれるマクロレヴェルの「創発性」ということができる.
進化型モデルの固有の存在意義は,与件を自己生成するという上記の特性の中にある.経験的にわれわれは,人間(ヒト)が固有の行動特性を持ち,あるいは社会が文化的な差異にかかわらず共通の構造,秩序を持つことを観察し,その観察事実を所与と考える.だがそう考えただけでは,当の行動特性や構造がなぜ社会に存在するかを説明する課題は達成できない.進化型モデルに基づくシミュレーションの意義は,そうした与件の成立根拠を推論することに求められる.
1.3.権力の理論
権力の存在は社会構造の普遍的特性の重要な1つである.むろん「中央政府」にあたるような権力がない社会はしばしば観察されている(Sigrist, 1967).しかし何らかの支配序列を持つことは,霊長類の社会の「文法」の1つといえる(Haslam, 1997).進化型の計算モデルが既述のように社会の与件を説明するものであるならば,権力という普遍的な社会構造特性の存在が進化型のモデルに委ねるべきことは自然な発想といえるだろう.
私見では,従来の権力の理論は権力の要因論とでも呼ぶべき理論だった.その典型が French & Raven (1959)の権力基盤(Bases of Power)の議論である.この理論(というより図式)は権力(勢力)の基盤として強制力,報酬,正当性,専門性,参照性,情報をあげ,それらの基盤に応じて対人的な勢力の強さが決まることを整理している.ある意味では M.Weber (1922/1947) の権力図式も,正当性の根拠に応じて権力を分類しているという点では,French らの図式と類似している.
従来の権力論の中で簡潔で強力な視点を提示するのが Emerson (1974a, b) の権力−依存(Power-Dependence) パラダイムである.この権力理論は,社会的交換において行為者Aが行為者Bに利得を依存するほど,Aに対するBの権力が強まることを述べる.Emerson の理論も,依存という権力を生む要因(French らの強制基盤と報酬基盤にあたる)を示したものであるため,権力の要因論の1つといえる.が,Emerson の議論が他の交換理論の権力論(e.g., Blau, 1964)より優れているのは,いち早く交換ネットワークの概念を明示し,交換ネットワークという構造的要因が権力を生み出していることを明示したことである.
しかし進化型のモデルを標榜する立場からは,以上のような権力の要因論は満足できるものではない.権力の存在を創発的に説明する訳ではないからである.権力の要因論が述べるのは,特定の行為者に要因や基盤が集まったときにその行為者に権力が生まれることである.しかしこの議論自体は何れかの行為者にその要因や基盤が集中することを説明するものではない.別のいい方をすれば,特定の行為者に基盤が集まることが動的均衡であることを述べる訳ではない.進化型のモデルによって権力の成立を説明するとは,まさに動的均衡として何らかのエージェントに権力(基盤)が集まることの創発的説明をすることに他ならない.その創発的説明が目指すのは,権力を内蔵した社会秩序がなぜ普遍的に生まれるのか,という問に答えることである.
権力が創発的に生じる経路はいくつかあるだろう.1つ考えられるのは,集団の機能として権力が生成される場合である.コミュニケーションネットワーク実験の集団のように,成員が目標を共有して協同する場合を考えてみよう.条件によっては,中心的な位置にある特定の1人に情報を集め,その1人が他の成員に指示を出すような体制が自動的に生まれる可能性がある(高木, 1999).このとき中心的な成員には集団機能としての権力が備わるだろう.また,より広い社会において,ある便益的な社会秩序の成立とともに特定の成員に権力が生じる可能性があるかも知れない.
集団機能として権力が生じる経路の中の重要な可能性は,各エージェントが特定のエージェントに「権限の委譲」をすることである.共有資源の維持・管理といった,個人的対処では解決できない問題に直面したとき,人間集団は「代表」に権限を委譲することは,実験的研究において知られている(Messick et al., 1983).さらに,Suleiman & Fischer (2000) は,集団間対立があるときに集団の代表者への権限委譲の様式によって集団間関係がいかに変容するかをコンピュータシミュレーションで検討している.権限委譲の仕方が集団間関係に影響を与えることは,逆にいえば集団間秩序の形成に応じて権限委譲の様式も創発されることを示唆している.
が,本研究が扱うのは,集団機能として権力が生じるという経路ではない.エージェント間の自発的な社会的交換の偏りから権力が形成される可能性である(2).
1.4.社会的交換による権力発生の説明
本稿が想定するのは交換ネットワークから権力が成立する経路である.
筆者がここで念頭に置くのは小説やコミックに描かれる劉邦(後の漢の高祖)や三国志の劉備の姿である.歴史上の劉邦から離れて,次のような架空の劉邦像を描いてみよう.まず劉邦は半ば侠客集団の中心人物として出発する.その時点での劉邦は仲間の世話をし,同時に仲間から協力を得る存在であった.つまり仲間の間での社会的交換が,劉邦を中心に発達していた(図1,(a)).しかしいったん劉邦が仲間から協力を安定的に得るようになると,他者には劉邦が仲間の協力を得る存在として映るようになる.仲間やその他の人から見れば,劉邦は個人以上の力を持つ存在となる.つまりもし逆らえば,自らに大きな被害を与える存在となる.このような過程を経て,劉邦は仲間の1人以上の存在となって行く.もはや他者の協力(あるいは服従)を得るのにその人に世話を与える必要はない(図1,(b)).強い権力を確立するのである.
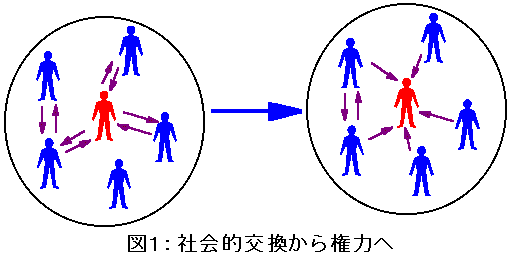
以上のアイディアをより公式に表現すれば次のごとくだろう(図2).人は相互になんらかの協力(労力)のやりとり(社会的交換)をする.さらに,人には多かれ少なかれ,相互の強弱に応じて他者を罰する能力(科罰能力)を持つと仮定する.しかし社会の中では労力の社会的交換において偏りができる.つまり交換に成功しより多くの交換に参加する者と,孤立する者とが生まれる.多くの交換に参加し他者の協力を得ることができた者はその交換相手から得る協力の分だけ強さを増し,科罰能力を高めるだろう.さらに,社会の中では誰が強い(科罰能力がある)かについての評判(reputation)ができあがるだろう.いったん「強い」と認知された者は,その科罰能力のために,自らは協力を供出することなく協力が得られるようになる.その結果得られる協力がさらに当人の権力を高める.このサイクルは適当な均衡点に達するまで続くことになるだろう.
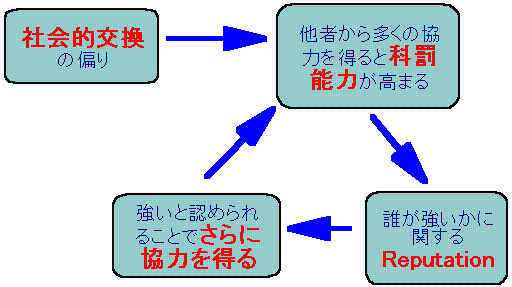
このように,本稿で想定するのは,権力の保持が権力の基盤になるという,権力の再帰的性格(recursivity)である.すなわち,社会的交換を経て他者の協力によって権力を持つというその事実が他者の服従をさらに促進し,権力を補強する,という点である.
ただし,以上のアイディアはあくまで言語モデルである.言葉の上では成り立つような気がする.が,ここで想定するような「誰かが権力を得る」という状態は,動的な均衡として整合的に矛盾なく到達できるのか? ― この点は言語モデルだけでは確定できない.以下では「交換から再帰的に権力が生まれる」というアイディアの論理的整合性を検討することを目的として計算モデルを作り,コンピュータシミュレーションによって権力の発生を検討しようとする.