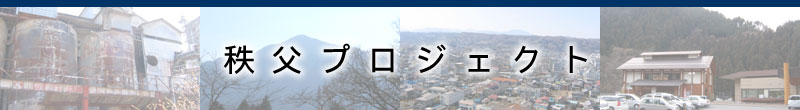| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第二章 秩父の観光 〜インタビュー調査を通してわかったこと〜 |
迫本紀美子
| 1.はじめに | |
| 2.調査の結果 | |
| * | 3.考察 |
| 4.おわりに |
3.考察
今回の調査によって明らかになったことは、秩父市は観光開発に積極的に取り組んでおり、行政、NPO、民間業者などが観光客増加を見込んだ様々な企画を立てている。その中でも、芝桜は、多くの観光客を掘り起こし、飛躍的に観光客が増加した成功例だと言える。しかし、冬は観光客が激減するなど、秩父市の観光業界にとって大きな痛手となっている。このような状況のなかで、持続可能な秩父観光を考えるにあたり、問題点は山積していた。
秩父市の観光戦略について、今回インタビュー調査を実施した印象では、観光に対する取り組み方について、それぞれの立場において、考え方の相違、温度差が浮き彫りとなった。
まず、行政の方とのインタビューでは、秩父は、精密機器の産業、農業などもあり、観光のみで生計を立てている人はわずかであり、観光に頼らなくてもやっていけるという意見があった。また、観光資源がなくても、人間が観光資源であり、人間同士のつながりを大事にしていきたいという意見もあった。さらに、秩父の観光はこれという決定的なものはないが、様々な観光資源が散在しているのが魅力ではないかという考え方もあった。しかし、積極的に他機関と連携・協同をはかり、秩父の観光をしっかりと確立していきたいという動きもあり、様々な催し物などが企画されていることが分かった。
次に、観光施設の現場で働いている方々へのインタビューでは、秩父にとって、観光は不可欠なものであり、さらに観光開発を進めていく必要があるという意見が大多数であった。しかし、秩父には目玉といえる観光資源がなく、今後の戦略について模索していることが分かった。また、行政との連携については、よくやってくれている、特に不満はないという意見が大多数であったが、具体的にはどのような施策があるのか把握していないケースがほとんどであった。中には、行政は何をやっているのか分からないという意見もあり、行政と現場との乖離が明らかになった。
さらに、道の駅ちちぶと秩父地域地場産業振興センターは、ほど近い場所に存在しており、競合している関係にあることが分かった。道の駅ちちぶは、駐車場などを充実させて、観光バスや、マイカーで秩父を訪れる観光客をターゲットにしている。秩父地域地場産業振興センターは、秩父駅構内にあり、鉄道利用者をターゲットにしている。また、新鮮な野菜なども販売し、地元客の来店も多い。加えて、様々なイベントや宅配、ネット販売などにも力を入れ、他店との差別化を図っていた。このように、各々の土産物屋の棲み分けも進んでいることが分かった。
秩父観光の現状として、日帰り客が中心であり宿泊客が少ないことが挙げられる。宿泊客が増加すれば、観光収益は大幅な増加が見込まれるであろう。宿泊地として観光客を増やすには、温泉が有力なファクターである。しかし、秩父市に温泉は点在しているが、まだまだ数は少なく、秩父観光に温泉というイメージは薄い。温泉のある宿泊施設の整備と、温泉地秩父というイメージを強力に植えつけていくことが今後必要になってくるのではないだろうか。しかし、日帰り客でも観光収入を増加させていく方法も重要である。例えば、釣り、キャンプ、句会など趣味的な活動のリピーターを増やす施策である。さらに、秩父といえば新鮮な農産物や果物が豊富である。現在でも多くの店舗で販売されているが、さらに売り上げを伸ばすには、秩父の土産物として統一したイメージを定着させていくことが有効であると考える。
このような現状の中で、行政と現場との観光に対する認識の差異、考え方の相違を埋めていかなければならない。これからの秩父の観光をよりよい方向へ発展させるには、観光は重要な秩父の戦略であるという行政側と現場の認識の一致が第一歩ではないだろうかと考える。
 |
 |