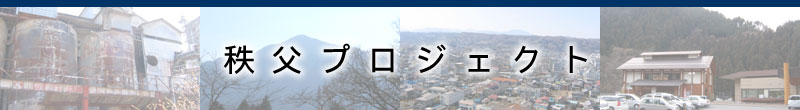| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第三章 秩父地域活性化のための産業遺産の活用に関する考察 -秩父織物とセメント産業- |
永井哲也
| 1.はじめに | |
| * | 2.秩父織物 |
| 3.セメント産業 | |
| 4.今後の秩父の活性化について ―産業遺産の活用― | |
| 5.おわりに |
2.秩父織物
2−1.秩父織物の歴史
秩父は四方を山々に囲まれ、平坦地が少ない場所である。そのため主食の米などの自給自足が難しい土地であり、古くから養蚕業が盛んな地域であった。江戸時代になると、貨幣経済が発展し、現金収入の副業として、養蚕−製糸−絹織物という家内制手工業の形で多くの農家に普及していった。また織物の普及と同時にたくさんの市が立ち、絹の売買が行われた。さらに経済・流通の発展に伴って江戸からの商人も集まり、絹織物は秩父の特産物として主要な現金収入となり、生活を支える重要な役割を果たすことになる。
その後明治28年には絹織物組合ができ、生産方式にも進歩を見ることができるようになった。明治の初期までは居座り機によっての製織だったが、その後高機(たかはた)に変わった。高機の普及により絹織物が無地物から縞物を織ることが出来るようになったことが、その後の秩父銘仙を生み出す要因となった。また当時生糸が貴重な輸出商品となっていた。そのため秩父織物には輸出商品にならないような玉糸を使い始め、そのことがも秩父銘仙を生み出すきっかけとなった。
 図1:秩父工業試験場跡(現ちちぶ銘仙館) |
■ | 秩父の織物産業の特徴として、資本主義的な産業革命を経ることなく産業が発達していったことが挙げられる。そのため小規模企業が数多くする企業形態がとられていった。大正時代には機械化が進み、織物工場は市内に500〜600軒もあり、人口の約7割が織物に携わっていた。大正9年に秩父を訪れた歌人の若山牧水は、街中から機音が聞こえてきた様子を「秩父町・出はづれくれば・機織の・唄ごゑつづく・古りし家並みに(※2)
」と唄うほど、織物産業が盛んであったのである。
|
2−2.秩父銘仙
秩父織物組合は明治41年に『解(ほぐし)模様銘仙』を創案し、解捺染という染色技術の改善、流行動向の把握等に努め、秩父の絹織物は「秩父銘仙」として大正から昭和初期にかけて女性たちの実用着、おしゃれ着として全国的な人気を博していくことになる。
解銘仙も縞銘仙も染色織物で裏表がないのが特徴であり、たとえ表が色あせても裏を使って仕立て直しが出来る利点があり、大変な人気を博した。
秩父銘仙が人気を博したもう一つの理由として斬新かつ大胆なデザインにあった。特に昭和初期の特徴はまさにモダンで、海外のデザインや日本の当時の画家のタマゴを採用することもあった。
そして秩父銘仙は銀座の街を闊歩するモダンガールやカフェの女給、女学生の必須アイテムとなっていったのである。
2−3.戦後から現代にかけての秩父織物産業
太平洋戦争の荒廃から立ち直り、昭和40年代には秩父銘仙の最盛期が訪れる。当時の経済状況も手伝って「ガチャマン」(ガチャっと一折すれば、1万円の収入が得られるという意味)という言葉が出来るほど、織物産業は盛んであった。しかしその後、年々工場数は減少していくこととなる(表1)。
理由として日本人が和服から洋服を着るようになったこと、安価な化学繊維が流入してきたこと、その安価な化学繊維に対抗するために、本物の絹でなく、レーヨンや人絹を代わりに使用してコストダウンを図ったことにより、秩父織物自体の質を低下させてしまったことなどが、秩父織物が衰退してしまった原因として挙げられる。また今日では斬新なデザインができなくなったことも要因と挙げられよう。
そのような状況の中で、平成に入って、静かな銘仙ブームが起こった。これは全国の家庭のタンスに眠っている秩父銘仙を回収し、改めて現代風にアレンジするなど秩父銘仙の復興を図ろうとしたのである。秩父の観光に多少寄与したものの、しかし、それはあくまで秩父銘仙の古着を扱っているに過ぎない。そのため織物産業にはほとんど還元されず、復興にむけた著しい成果をあげることはできなかった。このようなイベントはいまでも年数回行われている。
表1.織物産業の変化
| 工場数 | 従業員数 | ■ | 工場数 | 従業員数 | ||
| 昭和41年 | 389 |
2580 |
昭和59年 | 165 |
770 |
|
| 昭和42年 | 369 |
2042 |
昭和60年 | 154 |
722 |
|
| 昭和43年 | 356 |
1960 |
昭和61年 | 148 |
606 |
|
| 昭和44年 | 333 |
1501 |
昭和62年 | 145 |
560 |
|
| 昭和45年 | 258 |
1163 |
昭和63年 | 126 |
532 |
|
| 昭和46年 | 222 |
1081 |
平成元年 | 101 |
481 |
|
| 昭和47年 | 213 |
997 |
平成2年 | 90 |
476 |
|
| 昭和48年 | 196 |
848 |
平成3年 | 89 |
420 |
|
| 昭和49年 | 183 |
773 |
平成4年 | 76 |
433 |
|
| 昭和50年 | 166 |
698 |
平成5年 | 68 |
382 |
|
| 昭和51年 | 173 |
538 |
平成6年 | 63 |
382 |
|
| 昭和52年 | 149 |
416 |
平成7年 | 62 |
375 |
|
| 昭和53年 | 134 |
408 |
平成8年 | 61 |
375 |
|
| 昭和54年 | 127 |
361 |
平成9年 | 60 |
330 |
|
| 昭和55年 | 119 |
299 |
平成10年 | 58 |
290 |
|
| 昭和56年 | 101 |
294 |
平成11年 | 56 |
284 |
|
| 昭和57年 | 184 |
895 |
平成12年 | 54 |
270 |
|
| 昭和58年 | 173 |
785 |
データ:昭和41年〜61年 秩父織物構造改善商工組合
昭和62年〜平成12年 秩父織物商工組合
| かつて隆盛を誇った秩父銘仙も、現在では1件の織り元を残すのみである。唯一の織り元は「へんみ」であり、秩父市黒谷に工場を持ち、西武秩父駅の仲見世通りに店舗を構えている。「へんみ」では秩父銘仙を家庭用品として販売せず、伝統民芸品として販売しているのみである。さらに後継者不足に悩んでおり、このままでは秩父銘仙の歴史は消滅してしまう可能性がある。 そのような中で、秩父織物商工組合が「秩父銘仙館」を運営し、将来に秩父銘仙を残そうと尽力している。しかし、この組合に参加している織物関係者で秩父銘仙を現在作っている工場はなく、藍染めや草木染をしている団体の方々が運営している。ここからも秩父銘仙が廃ってしまい、秩父で織物産業が衰退していると感じることができる。 |
■ |  図2:ちちぶ銘仙館 |