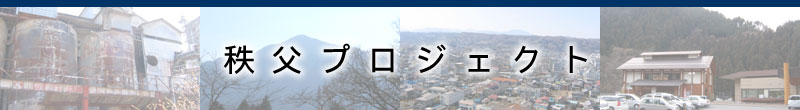| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第三章 秩父地域活性化のための産業遺産の活用に関する考察 -秩父織物とセメント産業- |
| 1.はじめに | |
| 2.秩父織物 | |
| * | 3.セメント産業 |
| 4.今後の秩父の活性化について ―産業遺産の活用― | |
| 5.おわりに |
3.セメント産業
3−1.秩父セメントの歴史
秩父織物と同様、秩父の産業の中心を担ってきたのが、武甲山から産出される石灰から製造されるセメントである。秩父地域ではセメントが産業としてスタートしたのは大正12年に秩父セメント株式会社(現秩父太平洋セメント株式会社)が設立されてからである。
戦後から高度成長時代を経て、セメントの需要は増加していく(表2)。秩父セメントの生産高は日本で屈指のものであり、供給地域は全国一の大市場である関東市場をはじめ、東北、信越、東海、北陸、および近畿地区までに及び、中でも工場立地上、関東市場に対する供給率は特に高い。そして秩父のセメント産業は昭和50年代が盛んで、何千人もの労働者の生活を支えてきた秩父の主要産業であった。

図3:ミューズパークから望む秩父太平洋セメント第一工場跡
| 前述したとおり、秩父セメント株式会社は大正12年に設立されたが、秩父工場(旧第一工場)が創業を開始したのは大正14年に入ってからだった。同社は埼玉県本庄市出身の諸井恒平が設立したもので、設立に当たっては諸井にとって同郷の先輩で、日本の近代化に貢献した渋沢栄一をはじめ、当時の財界有力者多数の援助と示唆を受けたものであった。特に渋沢の「国富の増進は地方産業の育成にあり」という考えは諸井に多大な影響を与えた。諸井は渋沢の助力を得て、秩父鉄道や武蔵水電等の会社経営に参画し、秩父地方開発に邁進していった。その中で秩父のセメント産業の基礎を築いていった。 その後、秩父セメントは関東大震災後の復旧工事、第二次大戦後の復興、高度経済成長を経て、わが国のセメント業界において屈指の企業となっていく。 |
■ |  図4:武甲山 |
3−2.秩父セメントと武甲山
秩父のセメント産業の発展には、秩父の象徴である武甲山の存在が欠かせない。秩父の石灰産業は江戸時代から存在していたが、製法が稚拙であったこと、原石には恵まれながらも山間部にある秩父の地理的条件に阻まれていたため、その搬出が困難を極めたこと、そして地元の利用度もわずかであったことから、産業としては発達していなかった。
しかし秩父セメントの発展とともに、武甲山における石灰の生産も飛躍的に増大していく。特に高度経済成長時代から1970年代にかけてセメントの需要が大幅に増加したことによって、武甲山の石灰の増産が図られた。昭和49年には武甲山で採掘をしている秩父セメント社、菱光石灰鉱業社、武甲鉱業社によって協調採掘に関する基本協定が締結され、昭和53年に武甲山の山頂開発に着手し始めた。
それにより武甲山の山容は大きく変貌する。それまで豊かな緑に覆われていた武甲山は、山肌を剥ぎ取られて白い岩肌を露出し、寒々しい姿をさらすようになってしまった。1336メートルあった標高も1304メートルになってしまった。
しかし、いまでも武甲山では毎日12時半に発破がかけられ、採掘が行われている。現在も武甲鉱業、菱光石灰、秩父太平洋セメントの3社が採掘を行っている。ただ景観の改善と崩落防止のために植栽が行われている。
90年代に入り、セメント業界の再編が盛んに行われていく。秩父セメントも例外でなく、平成6年には小野田セメントと合併し、秩父小野田セメントとなった。さらに平成10年には日本セメントと合併し、太平洋セメントとなる。平成12年には元秩父セメントが秩父太平洋セメント株式会社という太平洋セメントの子会社としてスタートした。そのような中で武甲山から採掘される石灰の量も秩父でのセメントの生産量も減少の一途をたどって、凋落が著しい。
上野原にある秩父太平洋セメントの第一工場は平成12年3月に休止になり、その後、同工場は閉鎖された。工場に併設された体育館は現在、「道の駅秩父」に変わり、昔7棟あった社宅用のアパートも次々に取り壊され、現在では入居者もなく3棟が残っているのみである。同じく併設されたグラウンドもいまでは老人たちのグラウンドゴルフ場となっていた。それ以外にも、昔食堂や浴場のあった場所は仮の秩父市議会議場になり、秩父セメントの埼玉事業所として使われていた建物も、今年9月に行われた衆議院選挙に無所属で立候補した議員の事務所として使われていたが、また無人の建物となっている。今後の活用 については工場の用地は秩父市が買い取り、再開発について検討委員会で討議中である。(※3)
| (※3)用地の活用について秩父市栗原市長は、秩父商工会議所の会報『商工秩父』において「ここ(第一工場跡)は新市域の将来の拠点であり、行政、市民の受発信の中核集積地として、長期的な考えを持って地主との交渉をしています」と述べ、さらに大型ショッピングセンターの進出については「市民の声が反映されない店舗の出店は難しくなるでしょう」と述べている。 |

図5:道の駅ちちぶの駐車場からの第一工場跡。手前右は秩父市議会仮議会棟 表2 秩父におけるセメント生産の状況
|
 |
資料:秩父太平洋セメント(株)
注1.石灰採掘量について
平成11年度までは三輪地区と生川地区の合計。
平成12年度からは三輪地区のみの採掘量とする。
注2.セメント生産量について
平成12年度までは第一工場と第二工場の合計。それ以降、第二工場のみ。