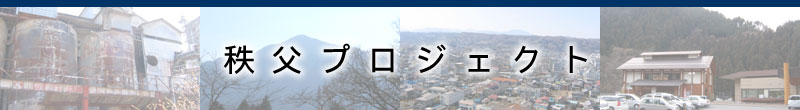| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第三章 秩父地域活性化のための産業遺産の活用に関する考察 -秩父織物とセメント産業- |
永井哲也
| 1.はじめに | |
| 2.秩父織物 | |
| 3.セメント産業 | |
| * | 4.今後の秩父の活性化について ―産業遺産の活用― |
| 5.おわりに |
4.今後の秩父の活性化について ―産業遺産の活用―
| 4−1.何故いま産業遺産か これまで秩父織物とセメント産業の変遷を見てきた。これら2つの産業は過去には秩父経済を発展させ、秩父に住む人々の生活を潤してきた。しかし時代の波には打ち勝つことが出来ず、現在織物産業は衰退してしまい、秩父銘仙にいたっては現在生産を行っているのは1件のみで秩父織物の再興は難しい。またセメント産業も石灰の採掘量、セメントの生産量ともに減少し、苦しい経営を迫られている。おそらく今後再興することも難しいであろう。 現在秩父市は地域活性化のために観光に力を入れている。その中で前述したとおり、地域の活性化にこの2つの産業遺構が寄与することはできるのではないかと私は考える。 例えば『日本経済新聞』の「プリズム現代・産業遺産は今」では、日本各地の産業遺産について取り上げている。(※4)その記事の一節では「今年(2005年)春から夏にかけて、関東各地で開いた産業遺産ウォーキング大会(日本ウォーキング協会、産業考古学会、日本経済新聞社主催)があり、8回の開催で、予想を超える延べ4000人余りが参加し、工場や鉱山跡、港湾施設などを歩いて回った」とあり、さらに「参加者の多くは60歳以上。高度成長を支えてきた高齢者にとって、産業遺産は懐かしい存在でもある。普段はウォーキングに縁のない人の参加も多かった」と書かれている 。(※5) これは秩父織物やセメント工場の遺構を産業遺産として一部でも保存し、維持・管理していけば潜在的な観光客を呼び込むことのできる呼び水になることを示している、と私は考える。 |
 |
4−2.秩父において産業遺産を取り上げるメリット
秩父で産業遺産を取り上げるメリットとして、秩父が織物産業、セメント産業の2つの産業を抱えている点である。産業遺産を活用して町おこしを考えている自治体は今日数多くある。例えば繊維産業の産業遺産を抱える群馬県富岡市や、銅山跡の産業遺産で抱える栃木県足尾町である。これらの街は1つの産業に特化して発展してきたが、秩父はそれらと異なり、織物工業とセメント産業の二つの産業によって発展した。二つの産業遺産を抱えるということは、私は強みであると考える。
なぜなら、例えば東京や千葉、埼玉などの人口が多い県から富岡と足尾の産業遺産を巡るに時間の制約があり、一日で観光するのは難しい。しかし秩父であれば、狭い秩父盆地に二つの産業があるためお互いが地理的に近く、二つの産業遺構を一日で観光することが可能であるからである。
また秩父地域には札所巡りや三峰神社、ほぼ毎日開催されている祭りや、春夏秋冬楽しめる花など、一年を通して楽しめる観光スポットに恵まれている。
さらに産業遺産として注目されることになると、案内役が必要になってくる。かつて秩父銘仙を織っていたOGやセメント工場で働いていたOBの人々が、案内役としてボランティアとなれば、高齢化社会の中で高齢者に新たな雇用が生まれ、地域振興に寄与するだろう。
ここでは秩父における産業遺産のメリットについて述べてきたが、続いて4−3、4−4において織物産業、セメント産業という二つの産業遺産を如何に活用していくのか、またその意義について、私の考えを述べて生きたい。
| (※4) 『日本経済新聞』2005年8月22日付夕刊〜9月5日付夕刊 (※5) 『日本経済新聞』2005年8月31日付夕刊 |
秩父では織物産業としての姿は薄れてしまったが、いまでも織物の街としての面影を見ることが出来る。織物工場のシンボルであるノコギリ屋根が、事業をやめてしまっていても倉庫などとして残っていたり、織物取引で賑わっていた買継商通りは昔の軒並みを残しており、その当時の雰囲気を感じ取ることが出来る。
また今日参加型、体験型の観光がはやっており、インフラを再び整備すれば新たな観光客層を呼び込める可能性があるのではないだろうか。
4−4.セメント産業の産業遺産の活用について
 |
旧秩父セメントの第一工場を残すメリットとして、経済発展を第一に開発を行い、環境を二の次にしてきた日本の姿と、地域の経済発展のために、信仰の対象である武甲山をいまの姿にするまで犠牲にしてきた秩父の姿がだぶるということが挙げられるだろう。これは日本の遺産として語り継いでいくこと重要であるということである。 その特徴として、環境を破壊してきたセメント工場と、被害を受けてきた武甲山が目と鼻の先にあり、視覚的に観光客に訴えやすいということがある。海洋汚染や大気汚染と目ではわかりにくい環境被害よりも、山の自然が失われ、痛々しい姿をさらしている武甲山の環境被害のほうが断然わかりやすい。今後持続可能な発展を達成していくためにも、過去の失敗から学ぶことが肝要であり、秩父のセメント産業はそのような教材となると私は考える。 |