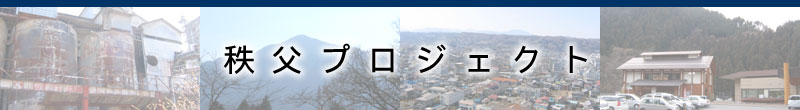| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第四章 観光資源としての秩父札所めぐりの可能性 |
手塚 雪香
| 1.はじめに | |
| 2.秩父札所の概要 | |
| 3.ヒアリング調査調査 | |
| * | 4.秩父札所めぐりの体験 |
| 5.秩父巡礼の動向 | |
| 6.調査結果からの考察 |
4、秩父札所めぐりの体験
4-1.調査目的・内容
実際に自分の足で札所めぐりをし、札所をまわっている人の立場から「札所めぐり」というものを実感・実体験する。実際に歩いてみることで、徒歩でまわる巡礼者の視点から気づくことや、改善できる箇所を発見する。
また、秩父を訪れ札所めぐりをしている来訪者の方へのヒアリングを行い、来訪者の情報を集めるとともに、歩いてみての感想や改善を求める点など生の声を聞くことを目的とする。
4-2.札所めぐり(1)
2005年9月14日(水) 14:30~16:30
|
この4ヵ所は西武秩父駅に近く、それぞれの札所も比較的近接した場所に位置しており、2時間ほどでまわれてしまう。
歩く道中、様々なモチーフを組み込んだ散策サインが設置されており、その散策サインを見つけながら歩くことや、まちかど美術館や「ちちぶ巡礼と民話のやかた」、「まつり会館」といった博物館を併せて巡ることも面白い。
町の中の札所をまわると、家々が建ち並ぶ中を歩いていくことになる。すると突然、昔からの家が並ぶ景観に出くわしたり、様々な発見をすることになる。
4-3.札所めぐり(2)
| 2005/11/20(日) 9:30~16:30 当日の行程 西武秩父駅―→栃谷―→第1番四萬部寺―→第2番真福寺―→光明寺(2番納経所)― ―→第3番常泉寺―→第4番金昌寺―→長興寺(5番納経所)―→第5番語歌堂―→ 第6番卜雲寺―→第8番西善寺―→第9番明智寺―→第7番法長寺―→西武秩父駅 |
■道に関して
・歩行者専用の巡礼道の中には、歩きにくい道もいくつか見られた。例えば、第2番札所から納経所への巡礼道は、登りの山道以上に急な下り坂になっている。その上舗装のされていない砂利道であるため、足の悪い人にとっては困難な道になっている。
・歩行者にとって危険な道。
 写真1 |
 写真2 |
|
■駐車場
・第6番は駐車場が遠いらしく、札所へ登っていく坂の脇に駐車。シルバー心材センター・ガイド班では、案内人の方が路上の駐車には気を使っているが、個人で訪れている人に関しては、個人個人の意識に頼らなくてはならない。道は広めで交通量は少なそうであるのでそれほど影響はないかもしれないが、近隣の方の迷惑になることもあるかもしれない。
■案内板
・案内板は3種類あり、札所と札所の間の長い道中では、道順や場所を示す道案内としての役割を果たしており、分かりやすく歩きやすくなっている。(写真3・4・5)
 写真3 |
 写真4 |
 写真5 |
・その他に、急で長いのぼり道が続く第1番から第2番への道中の道脇の木には「あと少し、がんばれ!」などの目印程度の手書き看板があり、疲れているなかで見ても微笑ましいものがあった。
ヒアリングをさせて頂いた方が仰っていた「秩父ののどかさ」が表われている一例ではないかと思う。
・また、これら新しい案内板と共に、辿ることで古い巡礼路が分かる300年前の「道しるべ石」が道中に点在している。300年前に巡礼の道となっていた巡礼路を感じながら歩くことや、道しるべ石を探しながら歩くことも楽しみになる。新しい案内板と共に、巡礼が盛んであった頃の面影を感じることができる。(写真 6・7)
 写真6 |
 写真7 |
■車のナンバー(チェックできたもの)
・車のナンバーには、熊谷、大宮、所沢と県内がほとんどで、他には足立、多摩、千葉、袖ヶ浦、湘南、群馬、が見られた。やはり、県内と近隣県から訪れる人が多い。
■風景
・第8番の「こみねもみじ」や第2・9番の「二度桜」、と四季をまたいだような風景を同日に見ることが出来る面白さ。
・私自身、札所について調べている中で、札所に咲く花や周辺の風景の写真を見て、「行ってみたい」という思いをもち、実際に訪れてもみじや桜を見て、札所で見られる草木や花を活かすことが魅力を作り出すことになると感じた。
実際に、今までに草花に関わる活動として行われてきたことは、
⇒市からの補助金により、4,5年前から花いっぱい運動を実施。
⇒秩父市内にある「ちちぶ巡礼と民話のやかた」では、それぞれの札所の代表的な植物は何かということや、それらの見頃はいつかという年間マップを展示している。
このように、花や樹木を、札所の見所のひとつとして宣伝していこうと考えている。この年間マップは参考になりそうなので、案内としてもっと利用すべきだと思う。
・秩父の札所では、おのおのに名物となる花や草木があり、紅葉や二度桜のような秋に見頃を迎える植物が秋の名物となっている札所もあるが、札所の多くは秋から冬に咲く草木をもたない。こういった時期には巡礼路の草木を楽しみにすることは非常に大きな効果がある。今回ヒアリングさせて頂いたほとんどの方の目的が道中の紅葉見物であったことからも、紅葉のもつ観光の要素が人を集めていると分かる。
■巡礼者同士の交流
・道中、どこが美しい景色であったか、紅葉の様子はどうか、お勧めの札所はどこか、どこのお蕎麦屋さんが美味しいか、といったようなことを道中で会った人と話し、言葉を交わすことで情報の伝達がされ交流が生まれる。
・特に歩いている方とは、札所や道中で何度も再会するので、更に親しみをもって交流が生まれる。
■地域の方との関わり
・第2番の札所から納経所へむかう間で、地域の長寿クラブの方が道中や寺院内に手作りの長椅子を設置(写真8)。地域の人だけではなく、歩いてきた巡礼者も座って休むことができる場所がある。―→地域の方が、お寺を大事にし、またそこを訪れる人をも大切に思っている気持ちが表れているよう。
・札所の近隣に住む地域の方は、札所に対して特別な意識をもっているわけではなく、日常生活に存在する近所のお寺という認識であるようである。また、ツアーにしろ個人にしろ、札所をまわっている人に対しての苦情は聞かれなかった。

写真8
―→シルバー人材センターや札所連合会のような札所との関わりが深い地域の方だけでなく、札所の近隣に住む方も、札所を秩父の観光の一つとすることに否定的ではないようである。札所への関わりの深さ如何に関わらず、地域の方の札所に対する意識に違いは感じられなかった。
4-4.来訪者へのヒアリング
○ヒアリングからみえてきた来訪者の特徴
・御夫婦二人で訪れている方が圧倒的に多い。
・関東内から訪れている。
・旅行日程は、ほとんどが日帰り。←関東ということと関係か。
・目的は様々であるが、紅葉などの風景を見ることを目的とする人が多い。
・初めて訪れた人では、知人の評判を聞いたという人も多い。
●御夫婦(東京から)(西武秩父駅から第1番までご一緒し、第4番でもお会いした)
旅行行程:日帰り
交通:電車で訪れ、徒歩でまわっている
すでに何回も札所をまわっており、今日は今年初めて。
札所の近所の方に話しかけたとき、育てている野菜を大量に分けてもらった。
●御夫婦(横浜から)(第2番から第3番へ向かう途中と、第8番から第9番に向かう途中)
旅行行程:一泊二日(1日目は札所めぐり、2日目は長瀞観光)
交通:電車で訪れ、徒歩でまわっている。
きっかけ:札所をまわった知人に「よかった」と紹介され、訪れてみた。
目的:何かのお願いがあったり宗教心というよりも、歩くことやその道中の景色を楽しむことを目的としている。
●女性二人組み(坂戸市から)(第2・3・5番にお会いした)
旅行行程:日帰り(1番から5番までまわり終了。)
交通:電車で訪れ、徒歩でまわっている。
目的:①今回で3回目。今回は、病気のリハビリのために歩いている。そのため、ゆっくりと自分のペースで歩いている。
第1番から第2番への山道を登ることで、日々の生活で大変なことや辛いことがあってもあの坂に比べたらなんてことはない、あの坂を登ったのだから大丈夫と思えるそう。
②連れの方に誘われ、初めて訪れた。
特に目的をもって来たわけではないが、道中の景色を楽しんでいる。
●御夫婦(群馬県太田市から)(第4・6番でお会いした)
旅行行程:日帰り
交通:車で訪れ、車でまわっている。
目的:第4番のお蕎麦屋さんで蕎麦を食べること。テレビ番組で取り上げられているのを見て食べに来た。そして、せっかく秩父まで来たということで、いくつか札所も見てまわっている(第1~7、10番の8ヶ所)。
●御夫婦(東京から)(第4番でお会いした)
旅行行程:日帰り
交通:車で訪れ、車でまわっている。
きっかけ:寺院関係の雑誌を出していた関係で秩父の札所と関わりがあった。お寺一ヵ所一ヶ所を単独で訪れていたが、今日のように続けてまわってみることは初めて。
目的:願をかけるというよりも、時期的に紅葉がきれいなので見物を楽しみにまわって
いる。
●御夫婦(千葉県から)(第5番でお会いした)
旅行行程:日帰り
交通:電車で訪れ、徒歩でまわっている。
目的:札所めぐりは5回目くらい。今回は今年初めて。
今回は、8番の紅葉と新蕎麦を目的に来た。
そして、これら目的地の間を埋めるようにいくつかの札所をまわっている。
今までには、時期によって桜や藤などを見ることを目的としてまわった。
秩父札所めぐりについて:
道案内の看板が整備されているのは、分かりやすくてよい。
また、道中の家先の植物を覘いたりできるのどかさが秩父のよいところ。
気になる点。歩車分離がされていないため、車を気にしながら歩かなくてはならない。
最近は車でまわる人も多いが、歩いてこそ気付くことも多い。車で点ばかりを訪れるのではもったいない。点と点を結ぶ線となる道にこそ面白さがある。