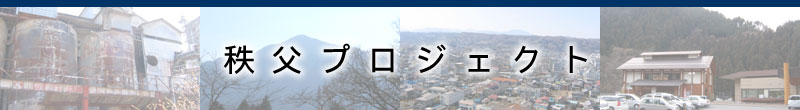| 目次へ | ||
| プロジェクト概要 | ||
| 調査報告 | ||
| 文化デザイン ワークショップ |
||
| 研究室NOWへ | ||
| 梶島研究室TOP |
| 第四章 観光資源としての秩父札所めぐりの可能性 |
手塚 雪香
| 1.はじめに | |
| 2.秩父札所の概要 | |
| 3.ヒアリング調査調査 | |
| 4.秩父札所めぐりの体験 | |
| 5.秩父巡礼の動向 | |
| * | 6.調査結果からの考察 |
6、調査結果からの考察
●秩父地域内のお年寄りの生きがい、QOL
→札所に関わることでの自信・誇り
→地元のお年寄り…新しく知識と経験をつむこと
自分の役割をもっていること 生きがい、生活のはり
シルバー人材センターと札所連合会の方々は、皆さん非常に元気で、自分のしていること・考えを生き生きと楽しそうに話してくださった。自信と誇りを持っている様子が伝わってきた。巡礼をする過程で定年後の道を見つける方がいるように、札所に関わっている方々にとっては、生涯の生きがいとなるものを見つけ、充実したQOLを実現されている。
また、シルバー人材センターの方は、札所の案内に対して料金が発生していることから、プロとしての意識を強く持っている。来訪者の中には巡礼に関する知識の高い人も多いので、そういった人たち以上に知識と経験を積もうと努力している。更に、札所のことだけでなく秩父地域のことも勉強することで、これまで以上に地域のことを知ることができたということも貴重だったと仰っていた。
●地元の方の意識、秩父地域内と地域外の人との関わり
札所は秩父観光にとっての一資源となる
→秩父の良さを知ってもらい、何度も訪れてもらえるようになれば。
大型バスなど多くの人が訪れることに悪い印象はない。
→地元の人の優しさだけでなく、気持ちの良い関係が築けるような互いの努力が必要。
札所を、秩父を大切に思っている皆さんは、秩父に来てここのよさを知ってもらいたいという気持ちを強く持っている。そのための橋渡し・きっかけとして札所巡りが観光資源としての役割を担うことは必要であると認識している。秩父には観光資源がないという方がいる一方で、札所に関わる職の方の中に、札所を一資源として認識されている方がいるということから、これから札所を取り込んだ地域づくりを考えていくことに充分余地があると感じた。
往々にして、住んでいる人にとっては、その地域の資源を特別に資源と意識することは少ないものであるが、秩父における札所も同じである。ずっと隣に存在しているものであり、人によっては檀家さんである。存在を意識するということもなく、札所ということを特別意識して生活はしていない。意識しないということは、札所から連想される来訪者に対する目立った悪い印象はないということでもある。
札所に関わりの深い方が悪い印象をもっていないというのはよく分かる話だ。では実際に札所の近隣住民たちは、住まいの近くにある札所に見ず知らずの多くの人がどっと押し寄せてくることに関してどう思っているのか伺ったところ、やはり同じように悪い印象はもっていないと教えてくださった。大型バスの進入や大勢の人が訪れることに思うところある方もいるかもしれない。しかし、地元の方々は広い心で受け入れているようだ。しかし、観光資源として活かすことを考えていくうえで、地域の方の理解は欠かせない。近隣住民の優しさに甘えるばかりではないお互いの努力が必要になるだろう。
秩父は札所同士の関係が近く、札所全体のまとまりがあるということなので、全体として動きを起こしたり何かを始めることがやりやすいだろう。
●福祉、健康・・・地域外の団塊の世代に向けて
→「歩く」、リハビリ
…比較的緩やかな工程であり、無理せず自分のペースで歩くことができる。
…巡礼路の草花や植物を楽しむこと
巡礼路を歩きながら秩父や札所の文化・歴史を辿ることができる面 等
複合的なアピールの仕方によって、様々な目的をもって訪れてもらえるように仕掛ける工夫。
団塊の世代が大量に定年退職し始めることや、急速に進む高齢社会において、福祉や健康はますます重要な社会テーマとなる。そこで札所めぐりという行為に、これからの生活に活きてくる役割がある。まず、シルバー人材センターや札所連合会の方々をみてもわかるように、生きがいや生活の張りといった精神的肉体的な活力を得られるということである。案内役として楽しみと緊張感の中で、自分の役割を持てることは、生活を豊かにするものとなる。そして、健康に関わって「歩く」ということの重要性は広く認識されている。巡礼の「歩く」行為は秩父札所めぐりを宣伝していく上で、大切なキーワードになる。秩父は全長約100キロの比較的緩やかな行程であるから、無理をせずに歩くことのできる巡礼路である。また巡礼という性格上、自分のペースで歩けばよいし、季節ごとの風景が歩く道程を楽しませてくれる。そして、歩くことに加えて、草花や植物、秩父や札所の歴史・文化を辿る道ということもあわせた複合的なアピールの仕方によって、様々な目的をもって訪れてもらえるような工夫をしていくことである。
山際の巡礼路は、草花や植物の景色を楽しむ古道、まちの中の巡礼路は、夜祭会館・まちかどミュージアムなどの施設も一緒に結ぶルート、というようなモデルルートを設定することもひとつの案になると思う。
●「点」の目的
→札所や特定の場所という点をまわり結ぶことで、必然的に秩父の中を線で結ぶ動きが生まれる。観光という観点からみたとき、地域内を線で結ぶ動きは重要。
特定の札所の紅葉や道中の風景、お蕎麦屋さんなど、秩父を訪れた目的は点であっても、併せて札所もまわってみようと考えている方が多い。自動車でまわってしまうと、各地の点にしか立ち寄れなくなってしまうが、徒歩で札所という点をまわり結ぶことで、必然的に秩父の中を線で結ぶ動きが生まれる。観光という観点からみたとき、地域内を線で結ぶ動きは重要と思われる。
調査結果からも明らかになったように、札所には多くの定年退職者がやってくる。新たな生き方を探しに来る人もいれば、山道を歩きながら自分のペースでゆっくりと時間を過ごしに来る人もいることだろう。まずは日帰りでも構わないので、多くの退職者を中心とする様々な目的をもって訪れる人たちを迎え入れる場であり、そこから秩父全体へと目を向けてもらうきっかけの一つとして秩父札所めぐりが一翼を担うものとなればよいと思う。
参考文献/佐藤久光『遍路と巡礼の社会学』人文書院、2004年。